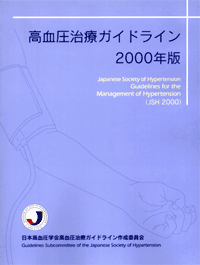
A4 判/125 頁/定価(本体 2,000 円+税)
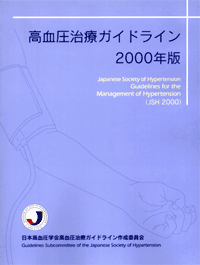
A4 判/125 頁/定価(本体
2,000 円+税)
高血圧は最も頻度の高い疾患のひとつであり、その結果生ずる心血管合併症は医学的、医療経済的だけでなく社会的にも大きな問題であります。特に、人口構成の高齢化が急速に進む本邦では、高血圧の早期診断と適切な治療はもちろんのこと、高血圧の予防は極めて重要な課題であります。
これまで高血圧治療のガイドラインとして、本邦では厚生省/日本医師会編の「高血圧診療のてびき」が1990年に発行されました。しかしその後、数多くの優れた降圧薬が開発され、また大規模臨床試験に代表される臨床成績が多数報告され、高血圧治療の考え方も大きく変わってまいりました。
欧米では、すでに世界保健機関/国際高血圧学会(World
Health Organization/International Society of Hypertension:
WHO/ISH)あるいは米国合同委員会(Joint National Committee on Prevention, Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure:
JNC)により高血圧治療のガイドラインが発行され、いずれも数年ごとに改訂されています。これらは世界的に広く利用されていますが、欧米と本邦とでは人種差、生活様式の違いや高血圧性心血管合併症の種類や頻度も異なり、欧米のガイドラインをそのまま適用するわけにはまいりません。そこで、日本高血圧学会では、日本人を対象にした実用的な「高血圧治療ガイドライン」を作成することを計画しました。
本ガイドラインの作成で特に留意した点は、(1)日本人を対象とした高血圧関連論文を極力盛り込むこと、(2)日本人特有の心血管合併症にも重点をおくこと、(3)高齢者高血圧の治療を独立した項立てとすること、(4)治療薬の選択は実用性を重視することなどです。また、本ガイドラインの概要を理解しやすくするために、各章に「まとめ」を設けました。
高血圧は、血圧のみならず、遺伝、環境、血行動態、内分泌・代謝異常などの多くの要因を介して全身の臓器に障害をきたします。高血圧の予防や治療を効率的に行うためには、食事療法や運動療法を含む生活習慣の修正や糖・脂質代謝異常などに対する理解と管理、さらに、すでに障害を有する臓器の循環動態をも考慮した高度に統合された治療戦略が必要であります。
本ガイドラインは、本邦における現時点での標準的な治療を目指したものでありますが、今後、高血圧学会をはじめ、他の関連学会や医師会などの評価を受け、さらに、次々に発表される大規模臨床試験の結果に基づき修正・改訂されるべきものであることは言うまでもありません。本書が高血圧治療に携わる臨床医の一助となることを願っています。
日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会委員長
藤 島 正 敏
序 文
第1章 緒言
1)日本人の血圧値と降圧治療の時代的推移
2)高血圧と心血管病、その治療の重要性
a)高血圧と心血管病の発症および予後
b)降圧治療の現状
c)降圧治療の問題点
3)公衆衛生上の高血圧対策
第2章 血圧測定と臨床評価
1)血圧測定
a)診察室、外来血圧測定
b)家庭血圧測定
c)24時間血圧測定
2)分類と評価
a)血圧値の分類
b)高血圧の重症度分類(リスクの評価)
c)予後評価のためのリスクの層別化
d)高血圧の病型分類
3)検査と診断
a)問診
b)診察(身体所見)
c)臨床検査
d)診断
4)初診時の治療計画
第3章 治療の基本方針
1)治療の目的
2)治療対象と降圧目標
a)治療対象
b)降圧目標
3)治療法の選択
a)生活習慣の修正
b)降圧薬治療
4)その他の留意事項
a)治療の継続
b)QOLへの配慮
第4章 治療I 生活習慣の修正
1)食塩制限
2)適正体重の維持
3)アルコール制限
4)脂質などの食事因子
5)運動
6)禁煙
7)その他の日常生活の注意事項
第5章 治療II 降圧薬治療
1)降圧薬選択の基本
a)第一選択薬の決定
b)降圧薬の変更と追加
c)降圧薬投与中の注意事項
d)薬物相互作用
e)降圧薬の減量と中止
2)各種降圧薬の特徴と主な副作用
a)Ca拮抗薬
b)ACE阻害薬
c)AII受容体拮抗薬
d)利尿薬
e)β遮断薬(含αβ遮断薬)
f)α遮断薬
g)その他の交感神経抑制薬−中枢性および末梢性交感神経抑制薬
h)古典的な血管拡張薬
第6章 特殊条件下高血圧の治療
1)難治性高血圧の対策
a)定義と頻度
b)難治性を示す原因と対策
2)高血圧緊急症および切迫症の診断と治療
a)定義と分類
b)高血圧性脳症
c)肺水腫を伴う高血圧性左心不全
d)重症高血圧を伴う急性心筋梗塞や不安定狭心症
e)褐色細胞腫クリーゼ
f)子癇
g)加速型高血圧−悪性高血圧
3)妊娠に伴う高血圧の治療
a)定義と分類
b)治療
4)外科手術前後の血圧管理
第7章 臓器障害を合併する高血圧の治療
1)脳血管障害
a)急性期
b)慢性期
2)心疾患
a)虚血性心疾患を合併する高血圧治療
b)心不全を合併する高血圧治療
c)心肥大
3)腎疾患
a)生活習慣の修正
b)降圧薬治療
c)透析患者
4)血管疾患
a)大動脈瘤
b)動脈硬化性末梢動脈閉塞症
第8章 他疾患を合併する高血圧
1)糖尿病
2)高脂血症
3)肥満
4)気管支喘息および慢性閉塞性肺疾患
5)痛風
6)肝障害
第9章 高齢者高血圧
1)高齢者高血圧の特徴
2)高齢者高血圧の診断
3)治療
a)高齢者高血圧の治療効果
b)降圧薬治療の対象と降圧目標
c)生活習慣の修正
d)降圧薬の選択
第10章 小児の高血圧
1)小児・青年の高血圧の特徴
2)小児の血圧測定と高血圧判定基準
3)小児・青年期における本態性高血圧の問題点
4)小児・青年期高血圧の病態
5)小児期における生活習慣の修正(高血圧の一次予防)
a)食事療法
b)運動
6)管理
7)降圧薬治療
第11章 二次性高血圧
1)腎性高血圧
a)腎実質性高血圧
b)腎血管性高血圧
2)内分泌性高血圧
a)原発性アルドステロン症とその類似疾患
b)クッシング症候群
c)褐色細胞腫
d)甲状腺疾患
e)副甲状腺機能亢進症(原発性)
f)先端肥大症
3)薬物誘発性高血圧
a)糖質コルチコイド
b)甘草(グリチルリチン)
c)経口避妊薬・エストロゲン補充療法
d)非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)
e)エリスロポエチン
f)サイクロスポリン
g)交感神経刺激作用を有する薬物
h)その他
4)その他
a)血管性(脈管性)高血圧
b)脳・中枢神経系疾患による高血圧
引用文献
巻末資料 降圧薬一覧
索 引
作成委員
委員長
藤島 正敏 九州大学大学院病態機能内科学
委員、執筆委員
猿田 享男 慶應義塾大学医学部内科腎内分泌代謝科
柊山幸志郎 琉球大学医学部内科学第三
日和田邦男 愛媛大学医学部内科学第二
荻原 俊男 大阪大学大学院加齢医学
竹下 彰 九州大学大学院附属心臓血管研究施設内科部門
江藤 胤尚 宮崎医科大学内科学第一
松岡 博昭 獨協医科大学内科学(循環器)
藤田 敏郎 東京大学大学院内科学
菊池健次郎 旭川医科大学内科学第一
島本 和明 札幌医科大学内科学第二
内山 聖 新潟大学医学部小児科学
事務担当
阿部 功 九州大学大学院病態機能内科学
評価・調整委員
金子 好宏 横浜高血圧研究センター
尾前 照雄 国立循環器病センター
荒川規矩男 福岡大学医学部内科学第二
飯村 攻 JR札幌鉄道病院
石井 當男 横浜船員保険病院
阿部 圭志 仙台社会保険病院
矢崎 義雄 国立国際医療センター
研究協力者
齊藤 郁夫 慶應義塾大学保健管理センター
村谷 博美 琉球大学医学部内科学第三
安東 克之 東京大学保健管理センター
森本 茂人 大阪大学大学院加齢医学
羽根田 俊 旭川医科大学内科学第一
浦 信行 札幌医科大学内科学第二
南 順一 獨協医科大学内科学(循環器)
北見 裕 愛媛大学医学部内科学第二
北 俊弘 宮崎医科大学内科学第一
廣岡 良隆 九州大学大学院附属心臓血管研究施設内科部門
土橋 卓也 九州大学大学院病態機能内科学
Copyright (C) 2000-2003 The Japanese Society of
Hypertension
Last modified on 2004/06/16
12:02 +0900