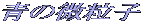
 |
星の話しだ。
ぼくたちはバーの高い椅子に座っていた。
それぞれの前にはウィスキーと水のグラスがあった。
彼は手に持った水のグラスの中をじっと見ていた。水の中の何かを
見ていたのではなく、グラスの向こうを透かして見ていたのでもない。
透明な水そのものを見ているようだった。
「 何を見ている?」とぼくは聞いた。
「 ひょっとしてチェレンコフ光が見えないかと思って 」
「 何?」
「 チェレンコフ光。宇宙から降ってくる微粒子がこの水の原子核とう
まく衝突すると光が出る。それが見えないかと思って」
「 見える事があるのかい?」
「 水の量が少ないからね。たぶん一万年に一度くらいの確立。それ
に、この店の中は明るすぎる。光っても見えないだろう。」
「 それを待っているの?」
「 このグラスの中にはその微粒子が毎秒一兆くらい降ってきている
んだけれど、原子核は小さいから、なかなかヒットがでない」
彼の口調では真剣なのか冗談なのか分らなかった。
「水の量千トンとか百万トンといった単位で、しかも周囲が真の暗闇
だと時々はチラッと光るのが見えるはずなんだが、ここではやっぱり
無理かな?」
考えてみると、この話をした時には、ぼくは彼とまださほど親しいわ
けではなかった。アルバイト先で知り合って、時おり飲んで、とりと
めもない話をするだけだった。どこに住んでいるのかも知らない。
いつも半ばは独言のよな彼の話しをぼんやり聞いていた。
「 微粒子ね 」
「ずっと遠くで星が爆発するだろう。そうすると、そこから小さな、ほと
んど重さもない粒子が大量に宇宙全体に飛び出す。何千年も飛行し
て、いくつかが地球に落ちてくる。いくつかって言うのが、このグラス
に毎秒一兆くらい 」
「 星か 」
「 そう、なるべく遠くの事を考える。星が一番遠い 」
「 遠くの事だね」 ぼくはまた繰り返した。
自分の頭蓋の内側が真暗な空間として見え、頭上から降ってきてそ
こを抜けてゆく無数の微粒子がチラチラと光りを放って、それをぼくは
単なる空虚でしかないはずのぼくの脳髄で知覚し、そのうちにぼくと
いうものは世界そのものの大きさにまで拡大され希釈され、ぼくは、
広大になった自分をはるか高いところから見下ろしている自分に気
付いた。
その静けさの彼方で、一人の男が一個のグラスを手にして、水の中
をじっと見つめていた。
池澤夏樹 「スティルライフ」より 中央文庫
|
|