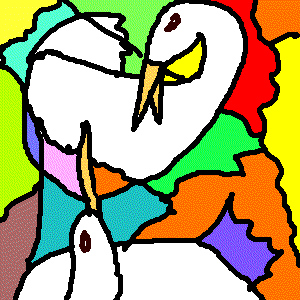丹頂鶴 |
|
|
|
石田三郎は食通家として知られていた。赤坂に高級料理店を開くまでになった三郎は、料理一筋でどちらかと言うと、食べること以外は何も関心のない男だった。
三郎の家は薩摩芋を栽培する農家だった。物心つくまで三郎はほとんど芋ばかり食べていた。 「もっといろんなものが食べたいなあ」 18歳になった三郎は母松代を残し、東京へ上京した。料理屋ならうまいものが食えると、料理店に住み込みで入ったが、来る日も来る日も皿洗いと掃除の雑用ばかりだった。料理は作れない。三郎は店の掃除をしながら、残り物の料理を隠れて食べた。その貪欲までな食べ物に対する執着心は、三郎をやがて名のある食通家へと押し上げていった。
三郎の所に、九州の松代からときどき宅配が届いた。梱包には松代からの添え書きがあった。 「三郎、元気でやってるか? あたしが作った薩摩芋が今年も取れたぞ」
三郎は段ボール箱から薩摩芋を取り出すと、生のままかじった。
「うまいよ、母ちゃん。だけど、俺、もっと、いろんなものを食べてみたい」 三郎は薩摩芋を食べるたびに幼いころの自分を思い出し、無性にうまい食材を求め、いても立ってもいられなくなった。そんな生い立ちが彼を奇妙な空間へと迷い込ませていった。 松代は、孫の顔を見たかったが、当の三郎は料理一筋でまるで女性に興味を示さなかった。心配した松代は、三郎のマンションへ見合い写真を持ってやって来た。玄関の呼び鈴を押すと、女の声がした。びっくりした松代は聞いた。 「三郎は? 」 「三郎様はお休みでございます」 「三郎の母です。入りますよ」 女は慌ててドアを開けると、松代を招じ入れた。松代はドア越しにその女を見てさらに驚いた。細面の鼻筋の通った顔立ちで、動作は優雅で繊細、思わず見とれて玄関先に立ち尽くしていた。「どうぞ」女の言葉で我に返った松代は、リビングに通されると、テーブルを挟んで女と対面した。 「あんたあの子の何だい? 」 「今は妻でございます」 「ほう、人にまるで無関心なあの子が結婚していたとは。しかし、三郎が関心を引くのも無理のない美しさだね。しかし、今は妻とは、どういう意味なんだね」 「三郎様はまもなく妻の私を忘れてしまうでしょう」 「訳の分からんことを言うねえ。三郎は一体何をしておるのだ。今日、あたしが来ることは知ってるだろう」 「はい、三郎様は隣におられます」 「なんだい、寝ているのかい、早く言っておくれよ」 「はい、昨日までは何とか歩いておりましたが、今日は歩くことは出来なくなり、ずっと寝ております」 「病気かい? そりゃ大変だ」 そのとき、リビングの隣で赤ん坊の泣き声が聞こえた。「失礼いたします」女は話を途中で止めると、リビングから続く部屋へ消えていき、あやしながら赤ん坊を抱えて戻ってきた。 「三郎様でございます」 松代は女の言葉に頭を傾げた。 「あれ、もう子どもまでいたのかい。それにしても、自分の子になんと自分と同じ名前を付けたのかね」 「いいえ、あなた様の息子の三郎様でございます」 「…… それを言うなら孫だろう」 松代は女の抱く赤ん坊を覗き込むと、今までの相好を崩し、赤ん坊のほほを指で軽くつついた。 「まあ、三郎そっくりだわ。あんたらいつ結婚したんだい。三郎はあたしに何も言わないで、しょうもない子だね」 松代は赤ん坊の小さな手をふしくれだった親指と人差し指で摘んだ。 「おお、可愛いのう」 赤ん坊をあやす松代を眺めながら、女は話し始めた。 「三郎様は北海道釧路の奥深い私たちの住む沼地へ一人でやって来られると、1週間ほど私たちの姿を飽きもせず見ておりました。私は人間を見るのは初めてでございました。父は構うなと申しておりましたが、どうしても、何をしに来ているのか知りたくて三郎様のお近くへ行ってしまいました。ただの好奇心から近づいて行った私は、三郎様と親しくなっていきました。いつしか私は三郎様を愛するようになりました」 「ちょっと待っておくれよ。しかし、あ、あんたの話は訳が分からんの」 松代の遮る言葉に女は深い悲しみの瞳を向けた。松代もそんなに悲しそうな瞳を見たことはなかった。思わず押し黙ってしまった。 「ただ、私の父は三郎様との結婚に反対をしておりました。三郎様は話せば分かるとおっしゃってました。あるとき、二人だけで話すと言って、沼地に張ったテントに父を招きました。私が明け方になっても戻らない父を心配して、テントのドアを捲り上げると、テントの中は鳥の羽が散乱しておりました。三郎様はうまいうまいと満足そうな顔をして、鍋から肉を取り出して食べておりました。私はその姿にぞっとしました。父の姿がないので行方を尋ねると、とっくに帰って行ったと申します。もちろん、結婚も承諾したと。落ちていた羽は父の羽根に似ておりましたが、それ以上、恐ろしくて考えることは出来ませんでした」 俯く女の瞳から涙が頬に流れ落ちるのを見ながら、松代はただただその奇妙な話を聞いていた。 「その日から、父は沼地から姿を消してしまいました。三郎様は悲しむ私の手を引いて、ここへ連れて来られました。3ヶ月前のことでございます。三郎様はいつものようにお店に通っておりましたが、1ヶ月前から、少しずつ三郎様は若返りを始めました。三郎様には父の呪いが掛けられていたのでしょう。やはり、三郎様は父を殺していたのです。私は三郎様を愛していましたし、今、この体には、三郎様の子がおります。人間の血が混じったこの子はいつか成長し、やがて死ぬでしょう。しかし、呪いを掛けられた三郎様は永遠に死ぬことはございません。ある年齢に達すると、若返り、赤ん坊になると、また、成長するのです。それを未来永劫繰り返すのです。私が三郎様を好きになったばかりにこのようなことになってしまいました。私は赤ん坊になった三郎様をこれからもお世話するでしょう。三郎様は若返るたびに一切の記憶が消え去ります。それでいいのです。私はこれからは妻としてではなく、三郎様の母として生きていきます」 「あ、あんたは…… 」 女は松代の言葉を遮るように、ソファを立ち上がり、着ていた服を一枚一枚脱いでいった。女の松代も目を見張るような、白い透き通るような美しい肌をしていた。生まれたままの姿になった女は、傍らの赤ん坊を抱え、窓際に歩いていった。 「ここから釧路までは遠くはありません。お母様お体にお気をつけて」 そう言って女は窓を開け放した。高層ビル特有の風がリビングの中に勢いよく入り込んで、松代は一瞬目を細めた。松代が目を開くと、逆光に立っていた女の姿が消えていた。赤ん坊も消えていた。窓辺に駆け寄った松代は、はるか先の夕日に鳥が飛んでいく姿を見た。松代にはそれが何と言う名の鳥かは分かるはずもなかった。 (あとがき) 丹頂の丹には次の意味があります。 薬のこと。多く、不老不死の薬をさしていう。 以下、小学館国語大辞典より抜粋 たん【丹】 Ⅰ
1 硫黄と水銀の化合した赤土。辰砂(しんしゃ)。また、その色。に。
2 鉛に硫黄・硝石を加えて、焼いて製したもの。鉛の酸化物で鉛丹ともいう。黄色を帯びた赤色で、絵の具とし、また、薬用とする。
3 薬のこと。多く、不老不死の薬をさしていう。 Ⅱ 丹波国(たんばのくに)、丹後国(たんごのくに)の略。 Ⅲ 〔語素〕丸薬・練薬の名前につける語。「万金丹」など。
|