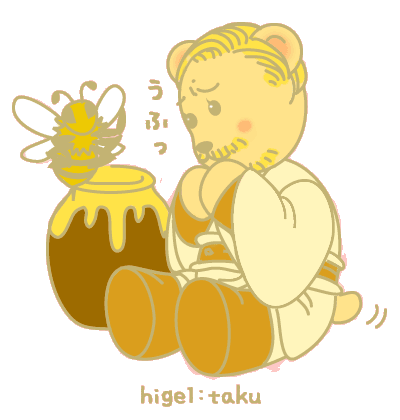ハニー・ハニー・ハニー 3
オビ=ワン・ケノービは、キッチンに立つ、弟子の後ろをうろうろとしていた。
弟子は、フライパンを片手に、キッチン中をいい匂いにさせている。
クマの鼻はぴくぴくとしていた。
フライパンからは、バターの焦げるいい匂い。
「アナキン、早く、入れるんだ」
オビ=ワンは、待ちきれなくて、ボールを持つ弟子を急かした。
クマは、弟子がボールに粉を入れ、かしゃかしゃとかき混ぜるところから、弟子の監督に余念がなかった。
今日は、オビ=ワンの好きなホットケーキがテーブル載る朝なのだ。
オビ=ワンは、週に4回早起きをする。
それは、一日置きということなのだが、これを、3回にするか、4回にするかで、師と弟子は、長く対立した。
オビ=ワンは、毎日でもいい、と主張していた。
アナキンは、それだけは、勘弁して欲しいと頼み込んでいた。
アナキンは、コンサルトに着いたばかりの頃、オビ=ワンの望み通り、毎日ホットケーキを焼き続け、実のトコロ、一時期ホットケーキを食べるどころか、匂いを嗅いだだけで、吐きそうになってしまった。
しかし、アナキンは、それでもホットケーキが嫌いにはならなかった。
それは、嫌いではなく、苦手だと思ってもいいと感じさせた幸運なチャンスがあったからだ。
あれは、まだ、パダワンだったアナキンが、熱を出して寝込んだ時の話だ。
高熱のため、うとうととしていたアナキンの枕元に、皿に載った真っ黒の円形のモノが置かれた。
アナキンは、びっくりした。
それは、とても焦げ臭かった。
しかし、その炭化した物体の上には、皿から溢れそうなほど、蜂蜜。
多分、ホットケーキのなれの果てだと思われる炭化物質は、オビ=ワンが大好きな甘い匂いもさせていた。
「……ア、アナキン、お前が作るようには上手くできなかったのだが、……でも、材料は、一緒なんだ。きっと食べたら旨いと思う。元気になるためにも、すこし食べてみないか?」
アナキンのベッドの脇に立ち、少し恥ずかしそうに弟子を見上げているクマは、前髪が焦げていた。
アナキンは、師の姿に驚いた。
だが、何本かの前髪をちりちりにしたクマは、自分の姿には頓着していない様子だ。
額に汗をにじませて、焦げたホットケーキを差し出すクマを、びっくりして見つめるアナキンの額を、オビ=ワンが触った。
クマの手は、柔らかく、ホットケーキのいい匂いがした。
「まだ、熱が高いな……。食べられるか? アナキン……?」
クマは、おずおずとアナキンに聞く。
食べられるか、どうか、と聞かれれば、アナキンには、オビ=ワンが差し出したものを食べられそうになかった。
熱のせいもあったが、いくら奴隷育ちといえど、これほど酷い料理を饗されたことがなかった。
オビ=ワンは、クワイガンの元で、パダワン時代を過ごしたはずなのに、料理が全く出来ないのだ。
なんと言っても、ぬいぐるみもどきのサイズであるオビ=ワンは、コンサルトの普及型キッチンに全く背が届かなかった。
勿論、今も、アナキンが料理を作っている。
クワイガンは、オビ=ワンに料理を作らすことを早々に諦め、代わりに、自分の周りに入れ替わり、立ち替わり現れる女達に、全ての料理を任せてきた。
おかげで出来上がった料理下手の美食家は、真っ黒な目を潤ませ、心配そうにアナキンを見つめていた。
自分だって汗をかいているくせに、師の手が、アナキンの額に浮かんだ汗をぬぐう。
「大丈夫か? アナキン? ずっと食べてないだろう? 少しでいいから、食べないか?」
「……マスター」
熱のある時に、ヒューマノイドが何を食べたいのかもよくわからないような師は、自分の好物を弟子のために作ってきたのだった。
焦げてはいたが、全く料理のできないクマの手作りホットケーキは、病気で心細くなっていたアナキンの心を慰めた。
きっと踏み台に上に乗って、料理にチャレンジをしたに違いない師の優しい心遣いがうれしかった。
アナキンは、だるい身体を起こした。
実のところ、もうその頃には、アナキンにとってホットケーキは、食べ飽きた嫌いな食べ物となっていた。
熱のために痛む喉も、ホットケーキのもごもご感を拒んでいた。
そして、なんと言っても、ホットケーキそのものが食べられないほど炭化していた。
しかし、黒い目を潤ませながら、一心に見つめるオビ=ワンにアナキンは、フォークを握った。
弟子は、フォークを刺すと、焦げ付き部分が、バリっという音をさせるホットケーキを口に運ぶ。
それに、蜂蜜の甘さはあったが、アナキンの口の中に広がったのは、苦みの方が多かった。
弟子の口の中では、ホットケーキを食べているとは思えないざりざりという音がする。
「……どうだ? 美味いいか?」
クマが、心配そうに弟子の目を覗き込んだ。
「……ええ」
アナキンは、喉に痛いものをなんとか飲み込んだ。
それは、美味い、不味いというレベルの食べ物ではなかった。
しかし、アナキンにとって、神聖な食べ物だった。
小さな師が、熱のある自分のために、危なっかしい手つきで作ったに違いないホットケーキなのだ。
そして、そのホットケーキは、アナキンにとって、新鮮でもあった。
熱のせいで、アナキンの味覚がおかしくなっていたということもあったと思う。
しかし、甘いホットケーキに飽き飽きしていたアナキンは、オビ=ワンが作った苦みばかりのホットケーキが面白い味だと感じだ。
アナキンは、多少の無理をしてだったが、オビ=ワンが作ったホットケーキを平らげた。
数時間後、熱だけでなく、腹痛も併発し、アナキンは苦しむことになったのだが、それも良い思い出だ。
ジュウっと、フライパンに広がったホットケーキの液に、オビ=ワンが嬉しそうに鼻をぴくぴくとさせた。
ぬいぐるみもどきのクマは、待ちきれなくて、踏み台を持って来て、それに乗るとアナキンの手元を覗き込む。
オビ=ワンがじっと見つめていると、フライパンの中のなめらかな表面に、つぷつぷと泡が盛り上がり始めた。
つやつやのオビ=ワンの目が輝いていた。
「ああっ。アナキン、もう少しだぞ。もう少しだ」
「マスター。まだ、早いですよ。もっと沢山、泡ができないと」
アナキンは、今にもよだれを垂らしそうなオビ=ワンを見下ろしながら、笑った。
ホットケーキは、また、つぷりと、小さな泡を膨らませた。
ぬいぐるみみたいなクマの口元が幸福そうにほころんでいる。
つぷり。つぷり。つぷり。
「マスター、今のうちに、蜂蜜の用意でもしたらどうですか?」
アナキンは、クマの頭がフライパンに近づき過ぎるのを心配して、声を掛けた。
しかし、アナキンが振り返ると、テーブルの上には、すでに蜂蜜の瓶が、ドンっと、置かれていた。
「マスター、ピッチャーに移し替えた分だけって訳にいかないんですか?……ああ、いかないんですね……」
泣き出しそうなクマの目に見あげられて、アナキンは、途中で自分の意見を曲げた。
どうせ、師は言いだしたらきかない。
フライパンの上では、ホットケーキが、つぷ、つぷと、また、泡を膨らませた。
つぷり。つぷ。つぷり。つぷ。つぷ。つぷ。つぷ。
あれほどなめらかだったホットケーキの表面は、もう泡だらけだ。
オビ=ワンの口が、はふはふと喜んでいる。
「あっ、割れた!」
泡が弾け出し、オビ=ワンが歓声を上げた。
「アナキン、アナキン!」
きらきらの目で見あげるクマの期待に、アナキンは応えた。
アナキンは、フライパンを揺すり上げ、ほいっと、ホットケーキを裏返す。
もう、アナキンは、ホットケーキならプロの腕前だ。
決して焦がしはしないし、かといって、焼け足りない等ということもない。
いつもふかふかで、甘くて、アナキンのホットケーキは、オビ=ワンの大好物だった。
「いいぞ! アナキンっ!」
フライパンにホットケーキが芸術的に納まって、オビ=ワンの興奮はさらに高まった。
クマは、踏み台の上でじたばたしている。
「マスター、お皿持ってきてくれますか?」
普段は、どんなことにでも、弟子を使おうとする師が、踏み台から飛び降りて、走って行った。
皿を差し出すオビ=ワンは、髭をひくひくとさせながらいい匂いのするアナキンのホットケーキを待っている。
アナキンは、皿の上に、ホットケーキを載せた。
オビ=ワンは、両手で皿を抱えて、テーブルに着く。
アナキンは、背後に声をかけた。
「マスター。瓶から直接かけるのは、許しませんからね」
「いいじゃないか!」
「確かに、壷で持ってこなかったというのは、進歩ですけどね。でも、だめです。そのままだと、蜂蜜がかかり過ぎになるでしょう?」
それほど、熱心でなく自分の分のホットケーキを焼いていたアナキンの背中を突くものがあった。
それは、ホットケーキを切るために用意されたナイフだった。
「ほんとに、もう。マスター……」
フォースを使って弟子を脅しつけているぬいぐるみもどきは、とても幸せそうな顔で、とろとろの蜂蜜をたっぷりとかけていた。
END