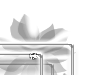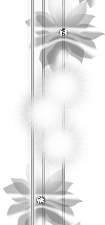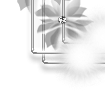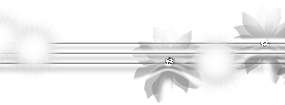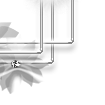気持ちが零れた
想いが溢れた
言うつもりだった言葉は飲み込まれ
言わないつもりだった言葉は投下される
言葉なんて所詮は上辺だけのモノで
そんなモノを信じていた自分が馬鹿みたいだと思った
片想い【28】
「あっ……」
玄関で白馬を見送って、新一は今日郵便ポストを覗いていないことに気付いた。
明日でも良いか、とも思ったのだが、有名な両親を持つと手紙類の数も半端無い。
勿論自分宛てに来るものもあるのだが、両親に比べればまだまだ少ない。
そんな有名な両親の所為でうっかり見るのを忘れると、配達員の人が明日困るであろう量が入っていたりするのもよくある事で。
「しょうがねえな……」
面倒ではあったのだけれど、仕方なく郵便ポストを覗けば案の定大量の封書達にげんなりする。
それを持ってリビングに行き、ソファーテーブルの上にばさっと放った。
その中で一際真っ白に輝く白い封筒に目が引き付けられた。
「まさか、な……」
そんな筈はない。
これが今日ここにある筈がない。
恐る恐る手を伸ばせば封筒には『工藤新一様』とだけ書いてある。
差出人の名はない。
ごくっと唾を飲み込み、封筒を開ける。
「何で……」
案の定中から出てきた見知った少し光沢のある白いカードに手が震える。
月神が守護する日から
軍神チュールが守護する日に変わる頃
今は無き小さな名探偵との最初の邂逅の地にて
平成のシャーロック・ホームズを待つ
月神が守護するのはそのままずばり月曜日。
チュールは主神オーディンの三番目の息子で、その名にちなんで火曜日はTuesdayと名付けられた。
とすれば、彼が示した時刻は今夜の0時。
余りにも分り安過ぎる暗号に慌てて時計を見れば、時刻はもう11時半を回った所で。
新一は小さく舌打ちをした。
ここからタクシーで向こうまで行っても間に合わないかもしれない。
慌ててポケットから携帯を取り出すと、いつも使っているタクシー会社の番号を押した。
「はぁ……はぁ……」
タクシーから慌てて飛び出した頃にはとっくに0時は過ぎていて。
それでも新一は慌てて階段を駆け上がった。
ドアを開けようとした所で、何だか奇妙な感覚に陥る。
昔このドアを開ける時はあんなにドアノブが高いと思ったのに。
あの時はドキドキしながら、必死でこの扉を開け、花火を持って彼を今か今かと待っていた。
余りにも懐かしい思い出にクスリと小さく口元に笑みが浮かぶ。
思えばあの時から、彼に惹かれていたのだろう。
一目惚れなんて信じていなかったけれど、確かにあの時自分は一目惚れをしたのかもしれない。
尤も……顔なんて知らなかったけれど。
意を決し、ガチャッとドアを開ければ―――その先には真っ白な衣装で凛と立つ彼の姿。
「よぉ、ボウズ…」
「もうボウズじゃねえよ」
「それもそうか」
地上の星を見下ろしたまま楽しそうに言うキッドに新一の口元も少しだけ上がる。
まるであの時みたいだ。
この手には花火はなく、自分の姿は大分変ってしまったけれど。
「こんな所に呼び出して、何の用だよ」
「せっかちだな、名探偵は」
踵を返し、新一に向き直ったキッドの瞳は、最後に見た時よりも少しだけ柔らかい気がした。
一歩一歩自分へと近付いてくるキッドを見詰めながら、自分の鼓動が煩いぐらいになっているのに嫌気が差す。
もう少し落ち着ければ良いのに。
もう少し冷静に彼と話せれば良いのに。
今日だって白馬の腕に抱きしめられながら、考えていたのは彼のこと。
最低だと知っているけれど、好きなのは…他の誰でも無い彼だ。
「るせーよ。それが呼び出しに答えて此処まで来た奴に対する態度かよ」
「確かに。まあ、あんまり期待しないで出したんだけどな」
「急過ぎんだよ呼び出しが」
「来なきゃ来ないで良いと思ってたんだ」
新一がむぅっと眉を寄せれば、キッドはそんな新一に笑みを向けた。
その笑みに、ぎゅっと胸が痛む。
ああ―――やっぱり彼が好きだ。
「どうせ白馬と一緒だろうから、気付かなきゃ気付かないで良いと思ったんだよ」
「何だよ、それ」
「いいんだ。名探偵は分らなくて良い」
「……それはそれでムカツクんだが?」
よりむうっと寄った眉に、キッドが笑みを深める。
こうしていると、まるであんな事など無かった様な気さえする。
明日になれば、全て元通りになる様な、そんな錯覚すら起こしそうな。
「名探偵らしいな」
「謎を謎のままにしとくのは性に合わないんだ」
「知ってるよ」
二人の距離が手を伸ばせば届く程になった頃、キッドは歩みを止め、ジッと新一を見詰めた。
その視線の熱さに、心が揺らぐ。
「なあ、名探偵」
「…何だ?」
何時に無く真剣な声色に、頭が警報を鳴らす。
何か――良くない気がした。
「お前は本当に白馬のことが好きなのか?」
「あ、ああ…」
「…………俺じゃ、駄目か?」
「えっ…?」
「……俺じゃ、アイツの代わりにはならないか?」
「!?」
言われた言葉に、新一は瞳を見開く。
余りの言葉に気持ちが…ついてこない。
「お前が白馬と付き合いだしたのは分ってる。でも俺も―――」
聞いてはいけないと思った。
これ以上聞いたら、きっと自分は壊れてしまうとも。
こんなのは嘘だ。
こんなのは夢だ。
絶対にこんな日は来ないと思って、あの日あの時あの言葉を言ったのに……。
「――――お前のことが好きなんだ」
欲しかった。
彼が。
願っていた。
彼を。
こんなに求めて求めてやまなかった彼からの『告白』が、こんなに胸に痛いなんて。
「どうしてもお前が白馬でないと駄目だというのなら、俺は潔く諦める。
でも……もしも、もしも俺でも良いと少しでも思うなら―――俺はお前が欲しい」
甘い言葉だった。
甘い夢だった。
新一が切実に願った未来が今目の前に広がっている。
ずっとずっと叶わないと思っていた夢が今現実になっている。
「名探偵。俺を選べ。俺ならお前が望む『謎』を幾らでも提供してやれる」
難解な暗号も。
ドキドキする様な現場も。
全部全部与えてやれる。
「俺を選べよ。そうしたら―――俺は一生お前を飽きさせない」
真摯な瞳でそう言ったキッドに抱き締められ、胸が詰まる。
どこか冷たそうだといつも思って見ていた彼は、酷く温かくて。
その温もりに涙が出そうになる。
このまま、彼の背に手を回し、自分も彼が好きなのだと言ってしまいたかった。
でも―――今の新一には既に選択肢などなかった。
自分の為に未来を捨てた白馬を今更捨てる事など出来ない。
彼を捨て、自分だけ幸せになる事なんて、絶対に出来ない。
自分は既に腹を括った。
目の前のこの彼を諦めて、白馬と共に居る事を望んだ。
自分の弱さが招いた過ちの責任は…自分自身が取らなくてはならない。
だからこそ、ここで彼に思いっきり嫌われておく必要がある。
もう二度と―――彼が自分に手を伸ばしてくれないように。
自分の中の想いを断ち切る様に、新一は思いっきりキッドを突き飛ばした。
「―――!」
少し後ろに揺らいだキッドの腕の中から、新一は慌てて逃げ出した。
これ以上彼の腕の中に居たら、決意が揺らいでしまう。
「無理だ。俺はお前を選べない」
「名探偵」
「だってお前は―――」
言えば全てが終わる事を知っていた。
言えば彼がどれだけ傷付くかも分っていた。
今自分は、彼の尤も触れられたくない部分を―――深く抉る。
「――――お前は、犯罪者じゃないか」
彼の目が大きく見開かれたのが分った。
次いで、泣き出しそうに揺らぐのも。
ポーカーフェイスであろうとする彼が、この姿でそんな顔をする所を新一は一度だって見たことが無い。
それだけに、自分がどれだけ彼の傷を抉ったのか分る。
「俺じゃなく、アイツを選ぶ理由はソレか……?」
ゾクッと背筋に嫌な物が走るほど、冷たい声。
そして、冷え切った彼の瞳。
硬質な藍が新一を捉える。
その瞳には、今にも凍えてしまいそうな悲しさが覗いていた。
「……ああ」
「そうか…」
唇を噛みしめた彼の表情は、苦痛に耐える様に歪められる。
顔を覆った手は、泣き出しそうな藍を隠した。
「そう、だよな……」
諦めに似た声が聞こえた。
顔を覆った反対側の手にぐっと力が込められるのが分った。
そして、最後に口元に諦めの笑みが上った。
「結局お前も同じか」
「キッド…?」
言われた言葉の意味が分らず、彼の名を呼べば再度その笑みが深くなる。
「結局お前も白馬と同じだ。親友面して、本当は最初からそういう目でしか俺のこと見てなかったんだろ?」
顔を覆った手が外される。
その瞳は――――余りにも冷たかった。
「俺は…」
「別にお前は悪くないよ。あの時の言葉を信じた俺が馬鹿だっただけだ」
「キッド…」
「忘れてたよ。お前が―――『探偵』だってこと」
言われた言葉には、言葉以上のモノが混ざっていた。
今までだって、キッドは嫌というほど、新一を『探偵』として認識していたし、新一もキッドの前では『探偵』であろうとした。
でも今言われているのはそういう意味では無い事を、新一は分り過ぎる程分っていた。
茫然とキッドを見詰めたまま立ちつくす新一に、キッドは微笑む。
『偽り』の笑みで悠然と。
そしてゆっくりと慇懃無礼なお辞儀を新一にして見せた。
「お喋りが過ぎましたね。今宵はそろそろお暇しますよ。またいつか、月の綺麗な夜に。さようなら―――工藤……探偵」
「っ―――!」
軽蔑する様な瞳と冷たい声に新一の心が軋んだ瞬間、視界が白い煙に包まれる。
その中で煙を払う様にもがいても、すぐにその煙が晴れる訳ではなく―――煙が晴れた頃には、当然の如く彼の姿はそこには存在していなかった。
「キ、…ッ…ド…!」
声が掠れる。
視界が歪む。
頬を伝い零れ落ちた涙が、アスファルトの地面に落ちて黒い点を作る。
確かに自分は彼に言った。
『俺は……お前がどんな奴だとしても―――友達だよ』
確かに自分が彼に告げた。
『例えお前がどんな奴で、何をしてたとしても――――俺はお前の傍に居る』
あの時の想いに嘘偽りはない。
今だって、そう思っている。
でも、だからこそ知っていた。
あの言葉が―――キッドを絶望に突き落とすことを。
彼は最後に自分を『名探偵』ではなく……『工藤探偵』と呼んだ。
それは彼から突き付けられた完璧な拒絶だ。
先に拒絶したのは紛れもなく自分。
彼を傷付けたのは紛れもなく自分。
けれど、彼の完璧な拒絶に、心がボロボロになっていくのが分る。
「キッ…ド……キッド………」
何度も何度も彼の名を呼ぶ。
愛しい愛しい彼の名を。
恋をしている。
愛している。
けれど、それをもう告げる事すら叶わない―――。
「俺は……お前が好き…だったんだ……」
その感情は――――紛れもなく『愛』と呼ばれるものだった。
to be continue….
top