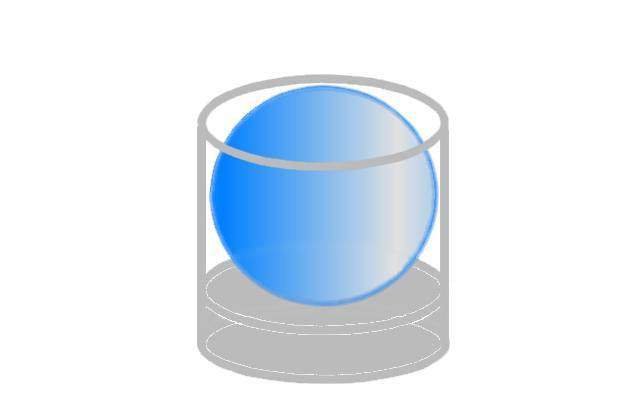
丸い氷でお酒を飲もう! 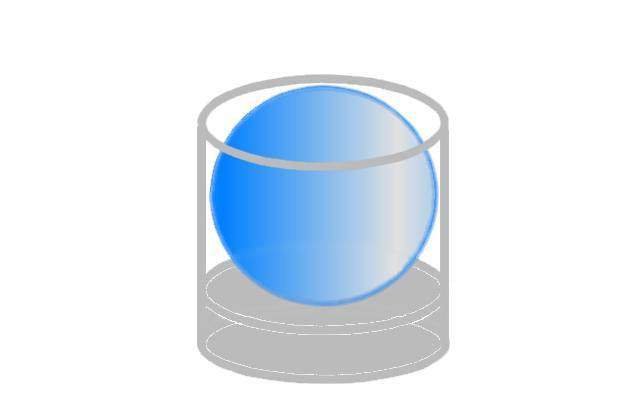
第4章 その2
第4章その1では、説明が足りないところがありました。
この第4章その2で補足したいと思います。
厚さ3cmほどの発泡スチロールを用意します(我が家の場合)。
まず、第4章その1で用意した断熱材を巻いた容器に一度沸騰させ冷ました水を
入れて冷凍庫で凍らせます。我が家ではこの時、先ほどの厚さ3cmほどの
発泡スチロールを下に敷きます。
1、こんなです。
ちなみに、この円柱の容器で作れる氷の大きさは直径9cm高さ16cmです。
透明な氷の作り方は上から徐々に凍らせます。一番下は凍らなくてもいいのです。
そのためには、発泡スチロールが必要です。
先日我が家で透明な氷を作った時、この発泡スチロールを敷かずに
失敗しました。
2、発泡スチロールを敷かずに凍らせた約48時間後。
写真の左が発泡スチロールを敷かずに凍らせたものです。
氷の底が凍ってしまいました。そのため気泡が下に行きづらくなりました。
白濁も発生し、そこの部分でひび割れもまた発生しています。
写真で私が紹介した断熱材の巻き方では、容器の底までは
断熱効果が不十分だったのですね。
いままでは発泡スチロールによって容器の底が凍らなかったのです。
右は発泡スチロールあり。
・ フラッシュあり撮影
・ フラッシュあり撮影
・ フラッシュなし撮影
写真の左が発泡スチロールを敷かずに凍らせたものです。透明な氷の部分が右のものに
・ フラッシュあり撮影
・ フラッシュなし撮影
氷の底が観察し易いようにひっくり返してみました。
写真の左が発泡スチロールを敷かずに凍らせたものです。右の氷は底が凍っていないため
水が抜けています。
・ フラッシュあり撮影
・ フラッシュあり撮影
上の写真の拡大です。
余談ですが、底が凍っていないと容器から氷を取り出すのが楽です。
容器をひっくり返すと水が落ちてくるので氷も自然と落ちてきやすいです。
3、解説
第2章で大まかに氷の作り方の考えを書きました。
水の最後に凍る部分が氷の内側になると凍る際の膨張の力の逃げるところが
なくなります。そして、ついにはひび割れてしまいます。
また、発泡スチロールを敷いても我が家の場合は冷凍庫の温度設定を
弱より強くすると上の写真の左のように底のほうが早く凍ってしまいます。
(弱、中、強)とあるダイヤルを弱と中の間にしてもということです。
以上の理由で、我が家では温度設定は弱で、発泡スチロールを敷いて凍らせています。
HOME
Copyright(c) 2006 zo All rights reserved.
Don't do reproduction of an image and a composition without
permission.