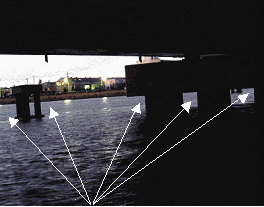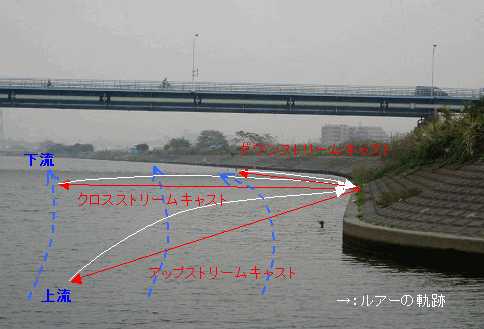メソッド
スタイル
一言に「釣り」といっても魚種によってはそのスタイルは様々。例えば渓流での鮎だったり湖沼でのマス系だったりすれば水に立ち入って釣る事がよくあるだろうし、海の堤防釣りであれば海に入ることはない。河口湖だったり霞ヶ浦でのブラックバスなんかはボートに乗って釣る人は多いだろうし、鯛釣りなんかも仕立て船なんかで沖に出たりもする。
ではシーバスは?
だいたいなんでもありです。
シーバス(スズキ)はもともと沿岸に生息する魚で干潟や河口、サーフなどの浅瀬、磯や湾など人が立ち寄りやすいところにいる。
| メソッド(スタイル) |
|
| ウエーディング |
ウェーダーを履いて水に立ち入るスタイル。干潟やサーフ、河川など立ち入れるポイントはさまざま。ただし自然の力をなめてかかると痛い目に遭うので立ち入るときには十分に注意したほうがよい。複数人で釣行すれば突発的なアクシデントにも対応はできる。 |
| ボート |
船で沖に出て陸から狙えないポイントを回るスタイル。 |
| 陸っぱり(おかっぱり) |
文字通り、「陸」から釣るスタイル。シーバシングは軽装備で出かけられるので「スニーカスタイル」なんて言う事もある。 |
| ラン&ガン |
陸っぱりの一部ではあるが、一箇所にとどまらずにシーバスが居そうなポイントを回りながら釣るスタイル。自転車や原付など小回りのきく乗り物があると効率よくポイントを回りやすい。 |
キャスティング
ルアーフィッシングのみならず釣りをするのであれば必ずおこなう動作は仕掛(ルアーや餌)を水に放り込むことであろう。メバルやチヌ(黒鯛)などで多用するヘチ釣り(岸壁際に仕掛を沈めて釣る方法)など仕掛を垂らすポイントは魚種により様々であるが、ルアーフィッシングは基本的に沖や岸壁、ストラクチャーにルアーを投げ込むのが一般的だ。
他のカテゴリでも勿論そうだがルアーフィッシングはポイントにルアーを投げ込む精度(キャスティング精度)は非常に高いものを要求される。橋脚やらストラクチャーやらピンポイントでルアーを落とさなければならないというシチュエーションはいたるところで発生する。また、流れを予測してやや上流側にオフセットをかけてキャスティングするなど状況によりアングラーが臨機応変に対応しなければならない。
下図のようなポイントを例に挙げてみると一般的に通してみる価値があるポイントが矢印の方向だとすると頭上には橋が架かっているためオーバーヘッドキャストではルアーを橋にぶち当ててしまうのでサイドスローがベター。橋脚の隙間に投げ込むには精度が必要になる。
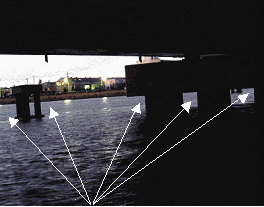
キャスティングの方法はいろいろとあるが、要は「どれだけ正確にシーバスに食わせたいポイントにルアーを通すか」これに尽きます。
野球の練習でバッティングセンターがあるように、ゴルフの練習で打ちっぱなしに行くように、キャスティング精度を高めるのは練習(or実践)あるのみ。
ポイントでは「あそこにルアーを落とそう」という意識を持ちながら精度を上げていこう。
| キャスティング |
|
| オーバーヘッドキャスト |
一般によく使われるキャスト法でルアーを投げるときにロッドを頭上から振り出す方法 |
| サイドハンドキャスト |
サイドスローのように腰の辺りからロッドを振り出す方法で飛距離を稼ぐには有効 |
| アップストリームキャスト |
流れの上流に向かってルアーを投げるキャスト法 |
| クロスストリームキャスト |
流れに交差するようにルアーを投げるキャスト法 |
| ダウンストリームキャスト |
流れの下流に向かってルアーを投げるキャスト法 |
キャスティングの方向は状況により使い分けるとよい。
基本的に魚は水流に頭を向ける習性がある。このため一般にはクロス、ダウンが多くなる。例えばクロスにルアーをキャストしても流れがあるので着水直後からしばらくはルアーは流される為、下流に頭を向けて泳ぐ。ある程度ラインを巻き取るとルアーはU字を描き今度は流れに頭を向ける。この流れに対して頭を下流から上流に向きを変えるシチュエーションでシーバスはアタックしてくることが多い。
また、バチだったり瀕死の小魚など泳力があまりないものが流されるシチュエーションを演出する場合は逆にアップ気味にルアーを投げて流れよりやや速めにリトリーブすることで釣果に結びつけることができる。
シーバスを多く手にするには「流れ」が重要なファクターとなる。
「流れ」を生み出す要素は潮汐そのものが支配的だが、風もこれに強弱を与えることがよくある。
例えば潮止まりに入っても風が強ければ流れを生み出すし、風の影響で中層と表層で流れが逆になっていたりもする。
シーバスは「流れ」を好む魚なのでポイントに到着したらまずこの「流れ」をよくみてみることだ。
、海中に浮遊しているゴミなどがどちらに流されているか見てみるのも潮流を知るひとつの手となるし、1投目はフローティングミノーなどを捨てキャストして潮がどちらに流れているか調べてみるのもよい。
まずキャストする前に「どの方向に潮が流れているか」は調べておけばきっと釣果に大きな影響を与えることだろう。
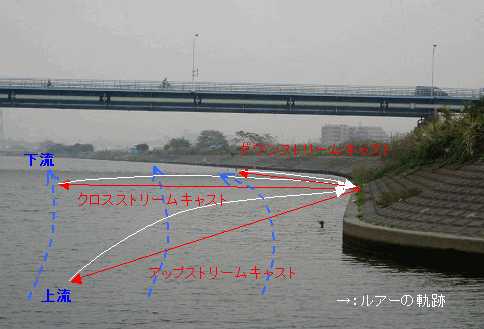
アクション
| メソッド(アクション) |
|
| ただ巻き |
一定の速度でラインを巻き取るリーリング法。特にロッドワークでルアーに余計なアクションを与えない。最近のルアーはただ巻きしてもある程度アクションをするように設計されている。 |
| ストップ&ゴー |
リールを止めたりしてリトリーブスピードに強弱を与えるリーリング法。スピードの緩急はシーバスに「獲物があそこにいる」と認識させるには効果的。ラインを巻き取って止まった瞬間にアタックをかけてくる(と言われている)。
「止める」といっても一般には1秒あるかないかという瞬間的な動作。
止める時間が長すぎたりすると見切られやすい。 |
| テクトロ |
カジキ釣りなど大物狙いトローリングの原動力がエンジンならシーバスのテクトロ原動力は『足』。
テクテクトローリングなので自ら歩いてルアーを泳がせる釣法。シーバスが着きやすい岸壁100mもテクれば1度はアタリがくる(はず)。
埠頭や都市型河川など足場のよい護岸で有効。 |
| トゥイッチ |
ロッドティップを小刻みに左右に振り、リトリーブ中のラインテンションに強弱を与えてルアーを左右に振るテクニック。シーバスへのアピール度が高いため、非常に有効なメソッドだが、テンションをかけるとノーズダイブを起こして見切られてしまう恐れもある。
あるていど明るい時間に練習してルアーごとのアクションを確認しておいた方がよい。 |
| ジャーク |
ロッドを振り上げてルアーにひら打つアクションを与えるテクニック。
弱った魚はのた打ち回ったり、浮上したりするのでこれに似せたアクションのため、シーバスも視認できたら淡々と狙いすましていることだろう。
大きくロッドを振り上げる場合もあればロッドティップを50cm程度「ピンッ」と引き上げる場合もある。 |
| ボトムバンプ |
バイブレーションやプレード系など底を探るルアーで海底を浮かせたり、コツっと底にあてたりしてシーバスにアピールするテクニック。基本的なロッドアクションはジャークだったりシェイキングだったりする。 |
| フォーリング |
シンキング系ミノーだったりメタル系で自重に任せて深めに落とす方法。シーバスは雑食性の高い魚種なので何でも食べる。基本的にベイトなどは浮上する傾向にあるが、これも意外性のある有効なアクションのひとつ。 |
| ドッグウォーキング |
トゥイッチよりもやや大きめのアクションでルアーを左右にひら打たせる。犬が歩くときにシッポを振る動きが由来。
ただし大きくラインテンションをかけるとシンキング系などリップのついたルアーはノーズダイブ(頭を下に下げる姿勢)になり見切られる可能性があるのでルアーがどう動くかは明るい場所で把握しておいた方がよい。 |
| リフト&フォール |
多少深さのある岸壁などで甲殻類(カニやエビなど)が落ちる姿に似せてロッドを徐々に上下させる方法。フォール中はラインテンションがかかりにくいので集中していないとアタリを逃しかねない。 |
| シェイク |
ロッドティップを上下に小刻みに震わせてルアーにアクションを与えるテクニック。ジャークほど大きなロッドワークは必要なく、小魚が瞬間的に推力を上げるようなイメージ、またはわずかに上下にのた打ち回っているような動きをイメージして操作する。 |
| 8の字 |
バチ抜けなど浮遊した虫類に似せて水面をクルクルと回して釣るテクニック。
ルアーを遠投するのではなく、手前、足元直下でルアーで水面に「8の字」を描くように遊んでみる手法。
水面を意識しやすいシーバスはこのときだすルアーの波紋を感じて食ってくるという。
常夜灯下だったりヨレ、タルミのできやすくバチがたまりそうな場所でトライしてみるとよい。 |
リトリーブスピード
ラインを巻き取るスピードでも釣果を左右することがよくある。
これは潮流の速さだったりポイントだったり、シーバスの活性などによりシーバスがアタックしてくるシチュエーションがいつも同じではないからだ。
リトリーブスピードは感覚的な部分が多いので個人差が大きいが、私はスローリトリーブであればダイワ2000番台のリールを1回転/2秒くらいで巻き取る程度で行っている。
デッドスローとなると最長で1回転/4秒程度。
| リーリングスピード |
|
| ファスト |
|
| ミディアム |
|
| スロー |
|
| デッドスロー |
|
*あくまでスピードに規定はありません。個々の感覚的なところが支配的ですので。実際にラインを巻いてどのくらいのスピードでルアーが泳いでくるか確認しておきましょう。

リトリーブスピードが極端に速かったり急激にラインテンションをかけたりするとルアーはノーズを下げた姿勢になる。ベイトフィッシュはフィッシュイータに追われたり、弱っていたりすると水面近くに浮上する習性があるため、この姿勢はシーバスに違和感を与えてしまう。
これはリトリーブスピードと潮流のバランスである程度決まります。あれこれ薀蓄を並べましたが、やはり経験によるものが大きいと思います。
とりあえず、「実践」からですね。
BACK