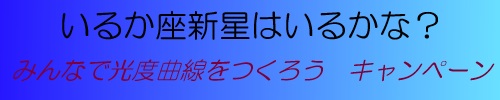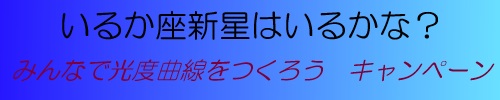いるか座新星はいるかな? >
GCVS編集長 サムシ (Samus') の新星の解説
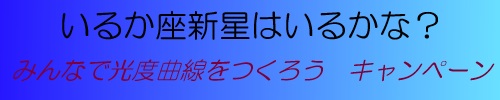
GCVS編集長 サムシ (Samus') の新星の解説
訳 :加藤 太一
我々の銀河系では毎年いくつかの(10個までの)新星が発見されているが、一般大衆の注意を引き、詳細な科学的観測に値するほどに明るい新星はその中でもかなり少ない。実際20世紀全体で最大等級2等よりも明るくなった新星は6個で、そのうえそのうち5つは20世紀前半だった。天文学者の若い世代全体がそのような明るい新星を一度も見ることなく育った。ここに20世紀の明るい新星のリストを爆発の年と最大実視光度とともに挙げる。
- GK Per (N Per 1901) +0.2
- V603 Aql (N Aql 1918) -1.1
- RR Pic (N Pic 1925) +1.2
- DQ Her (N Her 1934) +1.4
- CP Pup (N Pup 1942) +0.2
- V1500 Cyg (N Cyg 1975) +1.9
このリストからわかるように新星は他の変光星と同じシステムで名前が付けられる。N Her 1934 のタイプの名前は暫定的、あるいは補助的な(爆発の年を強調する)名称である。変光星の研究の初期には、決して消え去ることのない星と一時的な天空の訪問者である新星の間に境界を引こうと試みられた。そのような境界は存在しない: 新星は再度爆発をするはずであり、極小光度で観測から光度が得らえるものは、爆発以外の時期でも変光するものである。変光星の命名システムは第二次世界大戦以降全ての新星に順番に拡張され、それが1918年のわし座新星に意外にも大きな番号(V603)が付いている理由である。名前の不一致を避けるために、現在は天文電報中央局とGCVS編集チームが発見後早期に確定名を与えることができるように努力している。しかし時には発見が何年も遅れることがある。例えば2002年、S. Yu. Antipin は爆発の時には気づかれておらず、モスクワとゾンネベルクの星野写真から明らかになった十分明るい1985年わし座新星(極大で9等級)の発見を告げた。
典型的な新星の光度曲線は次の部分に分けられる。
- 1. 爆発までの状態。通常わずかに変光する星である。爆発前の期間については後にさらに詳しく述べる。新星前のステージは図3.1でa で示されている。
- 2. 光度上昇期(速い新星で数時間、最も遅い新星で2-3日)。図3.1では b で示されている。
- 3. 光度停滞期(訳注: premaxmimum halt) (v) 最大光度の2等下に達した時。光度停滞期の期間は星によって大きく異なり、1.5から40日である。最も速い新星、たとえばV1500 Cygではこの段階ははっきりしない。
- 4. 最終増光(g)と最大光度の段階。もちろん最も明るい光度になる時のことを意味している。しかし最大光度期として非常に速い新星で数時間、最も遅い新星で100日から数年に渡るまでを指すこともある。
- 5. 初期減光で、最大光度から3等級の減光までとされる(ステージ d)。
- 6. 遷移期 (transition phase) (e)。これは光度が単調に減光してゆく中での突然の傾きの変化であったり、振動期であったり、深い減光とその後の復光であったりする。
- 7. 最終減光(zh)。この段階では光度は一層小さな傾きで十分なめらかに減光する。何年間か後には新星の光度はおおよそ爆発前の値へと減光する(z)。
実視あるいは写真等級での変動の振幅は6等以上で、平均10-11等である。速い新星では遅い新星より振幅が大きい。最大の振幅は歴史上最も速い新星だった V1500 Cyg で記録された。最大光度でこの天体はV=1.9に達したが、爆発までどのようであったのかわかっていない。限界等級21等のパロマー写真星図にも写っていなかった。現在は V1500 Cyg は大変暗いが、それでも20等より明るい。
GCVSで採用されている新星のサブタイプは初期減光の速度に基づいている。初期減光の期間が100日かからない場合を NA型とし、初期減光が150日以上かかる場合を NBとしている。中間型のNABにはGCVSではただ一つのV400 Perだけが分類されている。NC型には非常に遅い新星が含められており(時にRT Ser型と呼ばれる)、最大光度の期間が何年も続く。それらの多くは後に述べる共生星新星の仲間である。
振幅と反復新星(NR)の次の爆発との間隔に重要な関係があることが判明した。反復新星という概念は相対的なものである。現在の推定では銀河系全体で一年で50-300個の新星が爆発している。最低の見積りであっても、爆発頻度を一定とすると10^10年の期間で5x10^11個の星が爆発しなくてはならず、これは全銀河系の星の総数を上回っててしまう。しかし原理からして全ての星が新星として爆発するわけではない。現在の考えでは新星は白色矮星を持つ近接連星系においてのみ起き得る。このことから新星は爆発を繰り返すことを結論することは難しくない。しかし大部分の新星では1回しか爆発が観測されていない。繰り返す爆発が観測されている星と典型的な新星の唯一の違いは現象の規模の小ささと振幅の小ささだけである。典型的な新星において繰り返しの爆発が観測されない理由は爆発の間があまりに長すぎるためであると推論することは自然である。
古代の年代記に記録されている中で私たちが典型的な新星として知っているものの過去の爆発があるだろう(そのような爆発の情報はGCVS第3版の第3巻にみつけられる)が、古代の年代記の位置の情報があまりに荒いためこのことを確信を持って結論することは難しい。このような事実は新星は爆発の際に破壊されるのではないこと、そして2点めとして振幅とサイクルの長さに関係があるはずであることを示す。
1930年代、B. V. Kukarkin と P. P. Parenago は U Gem型変光星(現在では矮新星と呼ばれることがまれでない)「平均のサイクルの長さと平均振幅」の関係式を導いた:
A = 0.4 + 1.85 log P
ここで A は写真等級での振幅でサイクルの長さ P は日で表されている。当時知られていた少数の反復新星について、Kukarkin と Parenago はこの関係が反復新星にも適用できるようだと結論した。当時1866年に爆発した T CrB が知られていた。この星の以前の爆発は観測されていなかったが、比較的小さな爆発振幅(8等)は反復新星に近いものであった。Kukarin と Parenago は1866年の爆発後80-100年で爆発を反復するだろうと推論する賭けに出た。星はその予言を汚すことなく、本当に1946年に爆発したのである。
この大変な成功を収めた科学的予言は、第一印象から思えるほどに、また長年に渡って教科書や一般科学書に書かれているほどには単純ではない。実際のところこの予言は異なる性質と爆発のエネルギー(Kurarkin とParenago はそれを知らなかった)を持つ別のタイプの変光星の特性に基づくものであった。さらに T CrB は反復新星のまったく典型的な代表というわけではない。白色矮星に降着する物質を供給するのは準巨星ではなく巨星であるため、そのため系全体の光量の中でより大きな成分を占め、その結果振幅が小さくなっているのである。しかしながら爆発の予言を出した祖国の研究者を正当に評価し、その先見性の成功を喜ぼうではないか。
新星爆発の測光的な描像を議論した後は、スペクトル現象にかかわることを見てゆく必要がある。まず言っておかねばならないことは爆発までの新星のスペクトルについての情報はあまり豊富でないことである。我々はまだ新星の爆発を予言する方法を知らない(しかし爆発を期待できる星については後に触れることになる)。知られている全ての古典新星は突然に爆発し、爆発までのスペクトルは普通星野を対物プリズムで大まかに撮ったものであり、すなわち分散やスペクトル分解能はは不十分である。私の知っている範囲では HR Del (N Del 1967) の爆発前に偶然質のそれほど高くないスリットスペクトルが撮られているだけである。
手に入る範囲の新星の爆発前のスペクトルは強い輝線のない
O型や B型を思わせるものである。多くの新星は爆発の進展の早い段階でみつけられるため、特に情報の不足はない。最大光度に達するすぐ前のスペクトルは吸収成分であるが、いくつかの吸収線に輝線を伴っている。輝線の相対的な役割は星がさらに明るくなるにつれて弱まってゆく。スペクトルは基準に基づいて普通の星と判断される可能性を排除するほどには特異なものではない。最大光度では新星のスペクトルはA または F型の超巨星に合致する。極大前のスペクトルにはすでに膨張するシェルを示す顕著な(1000km/sまで)負の視線速度が記録される。
極大後の新星のスペクトルは、これから個別に述べてゆくように、視線速度の値で区別される、あるスペクトル線システムから別のものへと進展するいくつかのスペクトル線システムが順次現れ、発達して消えてゆくことで特徴づけられる。最大光度からだいたい0.6等暗くなるといわゆるprincipal spectrum が現れる。もしスペクトル分類を試みるとすれば最大光度の時期よりはスペクトルクラスは早期でない。極大後ほぼ1.2等暗くなると diffuse enhanced spectrum と呼ばれるスペクトルが出現する。その特徴は広い H I, Ca II, Mg II, Fe II, Ti II, Cr I, O I, Na I の吸収線で principal spectrum に比べて(スペクトル線の)偏移が1.5-2倍大きい。その後2.1等ぐらい暗くなると orion spectrumと呼ばれる段階が訪れる。これには非常に広い He I, N II, O II, H Iの吸収線が存在し、後に N III、時に N V の線が現れる。orion spectrumの線の偏移は diffuse enhanced spectrum で観測されるものと同じオーダーであるが、いくつかの例ではずっと大きい値を示している。
新星のスペクトル線システムは広がった外層の中でのガスの集まり(gas condensation)の動きを反映している。星の光度が極大に比べておよそ4.1等級暗くなると吸収線が現れたのと逆の順序で消えてゆく。最後に消えるのが principal spectrum の吸収線で、principal spectrum の輝線が残る。星雲期の到来である。星雲期は極大からほぼ7等暗くなった段階で最も発達する。この段階の新星のスペクトルは惑星状星雲のものに似ており、この時期の名前の由来である。我々がスペクトルを観測している星雲は飛ばされた星の外層である。爆発から数十年を経過して星雲は直接観測できるようになる(fig 3.2)。その後空間へと拡散してゆく。
新星のスペクトルの発達途中に現れるシェルにおける現象の天体物理学についてはモノグラフシリーズ第5巻の「爆発型変光星」論文集におけるV. P. Arkhipova and E. R. Mustel' の論文で議論されている。(訳注: 1970年発行の本。国内図書館にあり)
新星爆発の物理的原因については現在天文学者の間でほとんど異論がない。一般に認められている解釈のアイデアは1970年代に R. Kraft が最初に提案し、S. Starrfield がそれを最初詳しい計算で確認した。爆発は近接連星の中の白色矮星の表面で限局していると考えられている。白色矮星はエネルギー源の枯渇した星で、核「燃料」が全て燃え尽きてしまっている。しかし伴星から流入する物質は、伴星が大なり小なり普通の星であるので(通常は準巨星)(訳注: 実際は主系列の方が多い)、白色矮星の表面によい核「燃料」である水素がたまってゆくことになる。水素の層の底部の温度が熱核反応を起こすに十分な条件まで上昇すれば、白色矮星表面で「水素爆弾」が爆発する。計算によればこの過程が可能になるには水素に富んだ物質の中にかなりの炭素と窒素が含まれている場合である。シェルの放出後は物質がまたたまってゆく。
新星が連星であることが確実にわかったのは Merle Walker が DQ Her (N Her 1934) が周期 4h39m の食連星であることを発見した1954年でであった(fig 3.3)。その後詳しく調べらたほとんど全ての新星や反復新星が測光的あるいは分光的に連星であることが明らかにされることとなった。
いつものように銀河系の構造の問題とも関連して。新星の絶対光度は興味深い問題である。極小光度では新星は非常に暗い天体である(これについては矮新星の極小光度の見積りを適用することができる。以下参照)。さらに多くの新星の極小はよく知られていない。なぜならば観測するにはあまりに暗いためである。そのため我々はまず第一に新星の極大絶対光度に関心を持つことになる。そして新星の極めて明るい光度、すなわち高光度(high luminosity)の天体は遠方における距離の指標として使えるかも知れない(たとえば比較的ちかくの銀河)。
1939年、D. McLaughlin は新星の極大絶対光度と極大後の減光速度との関係を発見した。より現代的なデータによれば(V. Pfau 1976)この関係は以下の形をしている
M(B)max = -10.67(+/-0.30) + 1.80(+/-0.20) log t3
ここで t3 (日) は新星が極大から3等減光するのに要する時間である。このように絶対光度が一番明るい新星は最も速く減光する。15日を経過すると全ての新星は比較的一定の絶対等級
M(B)(15d) = -5.76+/-0.60
を示す。M(B)(15d)の値はしかしまったく不変とは考えることはできない。この値はある程度 t3 にも相関がある。
現代天文学で観測されている期間に散開星団における新星爆発は記録されていない。いくつかの新星は球状星団に知られている。まず第一に 1860年のM80 = NGC 6093 星団における新星 T Sco を挙げなければならない。Christine Clement の球状星団変光星カタログの直交座標では星団の中心との距離は 4.8" である。星団中心と星の位置の違いはこれほど小さいが(一見して誤差範囲のように見える)、信頼できる測定である。いずれにしても星団のこれほど中央に存在することは、偶然重なって見える天体である可能性をほとんど完全に排除することになる。この星は実視光度7等に達した。1938年 Helen Sawyer が再構成した光度曲線ではこの星は速い新星であった(訳注: JRASC 32, 69 超新星との関連を論じている)。極大光度は観測で十分よくカバーされており(発見3日前には見られておらず、発見日と翌日はほぼ同じ光度で、その後急速に減光した)。T Sco がこの星団に所属すると仮定すれば M(V)max = -8.5+/-0.4が得られる。このような明るい絶対光度は速い新星に属することと一致する。
1938年球状星団 M14 = NGC 6402 の中心から約30"離れたところで新星が爆発した。残念なことに新星が写っていたプレートは1964年まで放置されていて、その時になってようやく A. Wehlau が新星を発見した。この星の極大は観測されなかったと推論せざるを得ない。一番明るい写真観測はほぼ16等で、星団に所属していると仮定すれば M(pg) = -1.5 に相当する。これは古典新星としては十分に明るくないが、研究者たちはこの星が星団の中の新星で、極大が見逃されたものと考える方を好んでいる。
時に球状星団の新星の第3の例として1943年に球状星団 NGC 6553 の中心から約5'離れて爆発した V1148 Sgr が言及される。この星は M. Mayallがスペクトル写真で発見したもので、概略の位置と3枚のプレートでのスペクトルの変化の短い記述が発表されているであり、古典新星のスペクトル進化の描像とはあまり似ていない。1970年代に Sawyer-Hogg がオリジナルのプレートを探そうと試みたが成功しなかった。球状星団の新星について語る時、私はこの星を数に入れたくはない。
M80 と M14 の2つの新星を星団のメンバーと考えれば、統計は非常に不十分と言わざるを得ない。しかし球状星団の典型的な質量を10^5太陽質量とすればおよそ150年で2つの星団に2つの新星が出たことから、形式的には単位質量あたりの爆発頻度を、銀河系全体をから見積もるよりもより近い値として(よりよいとまで言えないものの)見積もることができる。銀河系の星野に比べて球状星団の中で新星爆発の頻度がより低いとする根拠はないことは注意しながら言ってもよいだろう。
新星が極大時に観測できる明るさに達する近傍銀河での爆発の情報から、さまざまな星の種族における新星の頻度について理解できるかも知れない。GCVS第4版の第5巻はさまざまな形態分類の銀河で発見されたいくらかの新星が含まれている。次の表では新星、反復新星、新星と確認されていないものを区別していない。
- M 31 (アンドロメダ銀河) (Sb) 391
- NGC 5128 (S0p) 16
- M 33 (さんかく座銀河) (Sc) 15
- M 49 (E2/S0) 8
- M 87 (Ep) 2
- NGC 205 (Ep) 1
- NGC 4365 (E3) 1
- 大マゼラン雲 21
- 小マゼラン雲 5
類似の、しかし少し異なる情報が 1970-1980年代に V. P. Arkhpova によって得られている。さらに後に総括された情報は私は見つけられなかった。
挙げられた値はそれぞれの銀河での爆発頻度に直接関係すると考えてはいけない。正しい頻度を推定するためには継続的な銀河の監視を可能な限り進める必要がある。M31 については1950年代に H. Arpがそれを行った。1972年、A. S. Sharov が Arp のデータを再解析してアンドロメダ銀河の周辺部での爆発数を見積もった。それによれば M31 では1年に31個の新星が爆発する。Arp は同時に M33 も追跡し、このさんかく座銀河ででは2年で1個以下の新星しか爆発しなかった。M. Della Valle は1990年代にArp と Sharov の評価を再検討したが、M31 の方がずっと高い新星爆発頻度を示す点は実質的に変わらなかった。もちろん M31 は M33 よりもずっと光度が明るいが、それでも新星は Sb型銀河で最もよく爆発すると言えるかも知れない。太陽近傍で観測される新星の頻度をもとに、銀河系と M31 で新星の空間分布が似ていると仮定した A. S. Sharov が得た我々の銀河系での新星爆発頻度の見積りは1年に260個だった(通常はそのうち10個を越えない数が発見される)。
Sharov の見積りはこれまでに提唱されている値のうちでおそらくもっとも高いものである。他の者は我々の銀河系で1年に50-100個と見積り、あらゆる証拠から銀河系の光度や質量が M31より小さいことにもかかわらず、この値は M31 に比べてさえも十分に多い。ここでは我々の銀河系が Sb型に属することが有利に働いているとの見方がある。おそらくSb型銀河が最も高い新星頻度を示すということは、これらの銀河で新星に関係があるとされている星間物質がよく発達していることに関係が求めることができるかも知れない。
銀河系における新星の下部空間(訳注:オリジナルはサブシステム、種族と空間分布を合わせたような概念のようである)構造を調べることはサンプル数が小さいことからそれほど簡単でない。B. V. Kukarkinは1949年他の研究者とともに銀河系における変光星の種族を研究し、それが非常に矛盾した特徴を持っていることをみつけた。新星の銀経分布は球状分布の特徴を持っていた -del log(D)/del R = 0.27 が、Z座標ではより平坦成分の特徴があり、古典セファイドの分布より少し平坦でないだけであった。
当時は新星爆発の本質的原因についての知識が事実上ない中で、Kukarin は新星の空間分布の観測的特徴を説明する機知に富んだ仮説を提唱した(今では完全に捨てられている)。彼は、原理的に新星爆発を起こすことができる星は球状に分布するが、爆発自身を起こすためには他の星たちか星間ガスと関与する特別の条件を必要として、これは銀河面近くでのみ実現されると推論した。Kukarkin は T Sco が球状星団に所属する考えを私には理解しがたい理由で否定した。後の研究は新星について少し小さな -del log(D)/del R の値を出した。
今では T Sco が M80 のメンバーであることを疑う者はいない。I. M. Kopylov は1955年、新星の分布が星間物質の特徴を有していると結論した。しかし Kukarkin のこのコメント「ほとんど全ての知られている明るい新星は銀河面の近くで爆発している」について争うことは難しい(これはまた理論的にも簡単に解釈できない)
ことは注意する必要がある。
銀河系での新星の分布を研究することは難しい一方で、外から眺められるために条件の良い他の銀河に注意を向けるべきである。統計的解析に十分な資料はアンドロメダ銀河でのみ存在する。1971年、A. S. Sharov は M31 の新星の空間分布について詳しい研究を行った。彼は下部空間構造が複雑な構造をしていることを示した。M31 の中心核の近くでは新星は球状に分布しており、等密度分布楕円体の長軸短軸はほぼ同じであった。中心核から距離 2-3 kpcでは下部空間構造は大きく変わり、星間物質の分布に合うようになる。M31 の最も外側の領域では新星の下部空間構造はおそらくもっと平坦になる。
銀河系のおける新星の下部空間構造を運動学的に調べることは、まず第一に新星の視線速度はシェルのものであって星自身の空間運動を表しているのではないことから困難になっている。新星の固有運動は新星が星間物質に所属する(訳注:運動において)との仮説をおおむね否定するものではない。
いくつかの爆発後の新星を観測するとさまざまな種類の変光が明らかになった。食変光についてはすでに触れた。新星での食はかなりまれである。それらは短い周期(数時間)と光度曲線のハンプが特徴であり、ある1軌道周期と別の軌道周期で曲線の形に厳密な再現性がない。DQ Her の食変光を1954年に発見したM. Walker は、この系(fig 3.3)と食変光星 UX UMa (fig 3.4) の著しい類似性に気づいていた。二つの星は非常に近い周期で(DQ Herで4h39m、UX UMaで4h43m)、極小の前と後にあるハンプ、食から出る時の増光部の非対称性、位相0.7でのへこみは(訳注:食だけではない)物理的変光を示している。このタイプの変光曲線は系にガス流と高温のガス構造がにあることで説明できる(以下を見よ)。しかし UX UMa は近年数世紀に新星に似た爆発を示していない。GCVS第3版の3巻を調べても、いくつかの爆発がおおぐま座(訳注:くまは雌のようです)で観察されているものの、UX UMaが古代に爆発したことは確実には言えない。B. V. Kukarkin は彼の学生に UX UMaが爆発していないか確認して夜の観測を始めるようにいつもアドバイスしていた(fig 3.5; 訳注:爆発すれば北斗七星が一つ増える!)。興味深いことに、新星や新星類似天体の正体に関する現代的理解では UX UMa はしばしばまもなく爆発する候補天体リストに残されるのである。私たちはまたこの疑問に戻ってくることになるのである。
始めて食のある新星として明らかになった DQ Her には別の種類の周期的変光が観測される。厳密にサインカーブ状の振動で周期は71s、振幅は0.02等である。最初はある種の脈動現象に関係があると考えられたが、今では DQ Her の白色矮星の軸のまわりの回転が現れているもので、中間ポーラー(以下を見よ)の親戚であると考えられている。およそミリ秒からさらに長いタイムスケールで、爆発していない時期の新星は速い不規則な変動を示す - flickering という。比較的ゆっくりした振幅10分の数等級の不規則な変動も認められる。
D. McLaughlinは新星の爆発前と爆発からの減光後の光度に差があるかという重要な問題提起を初めて行うとともに、まもなく爆発があることを「予言」できるか、光度変化に何らかの「前兆」のかそれとも増光は急激にまったく突然に起こるのかを問うた。
1949年、新星の光度曲線の研究をしていた E. B. Kostyakova は多くの物に爆発前の増光が見られることを見つけた。すなわち光度が0.4等かそれ以上(数等級まで)しばらくの期間(5年まで)爆発までに増光が見られることである。さらにいくつかの星では2回の爆発前の増光が観測された。爆発前の増光の振幅と、爆発前の増光から主爆発までの時間間隔の関係が明らかになった。爆発前の増光が強いほど、主爆発までが近いのである。Kostyakova のこの正直に言えば忘れられた結果は1975年、V1500 Cyg の壮大な爆発の後に思い出されることになった。すでに触れたように V1500 Cyg は写真等級および赤等級で限界等級21等のパロマーチャートには写っていなかったのである。爆発の2週間前、シュテルンベルク天文学研究所のクリミア観測所で偶然(ミスで!)プレートが撮影され、新星は17等ぐらいで写っていたのである。私はこのことを爆発の翌日に見つけ、IAUCに報告した後、他の天文台でも同様に写真がみつかり、爆発の23日前から始まった V1500 Cyg が徐々に増光してゆく経緯を追跡することができた。ゆっくりした増光(爆発前の増光?)の全体の振幅は7.5等以上で、主爆発の直前に起きたことから Kostyakova が発見した関係を確認することになった。E. B. Kostyakova 自身は1975年終わりに、以前に関係を見つけた図にV1500 Cyg をプロットした短い報告を発表した。
はくちょう座新星は空で輝いている一方、天文学者たちは McLaughlinの体系を否定する E. Robinsonの大論文がちょうどうまく出た Astronomical Journal の最新号を読んでいた。Robinson は爆発までに何らかの写真観測を見つけ出すことのできた33個の新星のカタログをまとめた。そのような星は大変少なく、1990年代になってようやく20等より明るい大部分の星についてのおおまかであっても測光データをまとめたカタログが現れたに過ぎない。12個の星についてRobinson は主爆発までの光度曲線を構築することに成功した。Robinson はカタログの全ての星を5分類に分けた。
クラス I (12天体) - 単によく調べられていない天体。
クラス II (9天体) - 爆発前の光度と減光した後の光度が知られているが、爆発前の光度曲線を作るにはデータが不十分な新星。これらの全ての星について爆発前と減光した後の光度は非常に近かった。
クラス III は爆発前にそれなりの光度曲線が得られ、光度曲線は
McLaughlin の古典的描像に収まる。すなわち爆発までは星は小さな振幅の変光星で、その平均光度は爆発の前まで変化しない。爆発前と減光後の平均光度は同じである。Robinson はクラス III に5個を含め、そのうち4個は1935年までに爆発したものだった。まさにこの4個の星から McLaughlin は主要結論を導いていたのだった。
(Robinson: http://adsabs.harvard.edu/abs/1975AJ.....80..515R)
クラス IV は5個の新星を含み、その光度曲線は小さいが、爆発の1年から6年前の期間に有意に明るくなっていた(0.25等から1.6等まで)。Robinson は「爆発前の増光」というという用語は使わなかった。このクラスには反復新星の T CrB が含まれていた。興味深い星BT Mon もこのクラスに入っていた。非常にわずかな写真には17等よりも暗く写っていたが、爆発の後数年は光度15-16等の間に入った。爆発後は光度は15.8等までしか下がらなかった。これは新星が最初のレベルで戻ることのない例として Robinson の言及した唯一の例である。実は、すでに当時 CP Pup の同様の挙動を疑うだけの根拠があったのである。現在爆発後 60年を経過しているが、この星は15.2等である。しかし爆発の直後の 1942年、古いハーバードプレートでこの星は17等よりも暗いことが報告されていたのである。この結果を確かめておくべきだったのだ。
V1500 Cyg もまたもともとの等級に減光しなかった上に、この星はやはり非常に速い新星である CP Pup との類推から爆発の早い段階からこのことが予言され、イタリアの天文学者 L. Jacchia はこれらの星は「生涯で」初めて爆発した星だと考え、「処女新星」という名前まで作りだしていた。しかし Jacchia の成功した予言はネイチャーの編集部にリジェクトされ、プレプリントの形で配布されただけだった。
クラス V には Robinson は2つの新星を登録し、特異であると考えた。一つめは V446 Her (N Her 1960) である。これについては 1971年、Stienon は爆発までの変動の特性と減光後のものが異なっていることを明らかにした。爆発まではこの星は2等の振幅で特徴的な時間20-30日で変動していた。爆発からの減光後は変動の振幅はたった0.1等しかなかった。これは星の測光的特徴が爆発からの減光後に変化する最初の例である。
Robinson の二つめの特異変光星である RR Tel は GCVS は NC型に分類しているが、古典新星とはみなしにくい。今ではこの様な星は共生星新星と呼ばれており、爆発の原因に関して新星のクラスが多様であると語る Robinson の見解を正当化するように見える。共生星については次の章で触れる。ここでは彼の興味深い出版物の紹介を完全にするために Robinson の述べた RR Tel の情報を述べることとしたい。RR Tel の変光にはこの星が新星のような爆発をするずっと前から知られていた。かつてはこの星は平均写真光度がほぼ14等で振幅2等までの不規則変光星であった。1944年に起きた爆発の15年前には変動は約387日で周期的な特徴を示した。変動の振幅は次第に増加して3.5等に達した。平均光度は爆発の数年前には15等まで暗くなり、その後爆発に至まで増光して14.0等になった。爆発ではこの星は7等まで明るくなった。爆発後のスペクトルには TiO帯が見つかっている。
あらゆる特徴からこの系ではスペクトル型 M5III の半規則(あるいはミラ型であるかも知れない)星が脈動している。387日周期の脈動の兆候は M. Mayall が爆発の時にさえ見つけた。興味深いことに1944年の爆発の後の減光は現在に至るまでまだ完了していない。P. N. Kholopov は、爆発前の光度まで戻らないことを分類上の最も重要な特徴とし、1970年代に共生星新星に対して RR Tel型という型名を導入した。同僚たちは、プロトタイプ自身である RR Tel が1944年の前の光度まで減光することを保証できない以上、そのような定義は受け入れられないと彼と論争した。しかしこの型名は別の理由から採用されなかった。RR Tel型と伝統的なNC型を十分に確信をもって分離することができないことがわかったのである。そうすればいずれにしても後者の分類には1-2個の天体しか残らなくなってしまうだろう。NC型サブタイプと共生星新星の関係は疑いないことであるが、新星の分類システムを厳密化することは将来の仕事である。