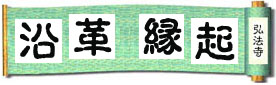
弘法寺は、約400年の歴史をもつ青森県日蓮宗の古刹です。
慶長十年(1605)、県内最古の日蓮宗寺院、弘前法立寺の第七世実成院日光上人が、薄市村(現在の中泊町大字薄市)に実成寺を創立したのが最初です。その後、中里村(現在の中泊町大字中里)に信徒が多数あったため廷宝元年(1672)四世日禅上人が、現在地に移転、寺号を実成寺より弘法寺に改称し、廷宝三年(1675)に本堂・庫裡が完成しました。
十二世日盛上人代の寛保元年(1741)に本堂・庫裡が修理され七面堂を再興し、永聖跡となりました。寛政十年(1791)に十六世日永上人が境内地を拡張し、東西八間、南北七間の本堂を再建しました。現本堂は、大正十年(1921)に二十九世日導上人代に新築されたものです。
境内には、山門、本堂、庫裡、鐘楼、三十番神堂、本堂裏山に七面堂がありますが、現在三十番神は本堂内に祀られ、鐘楼の梵鐘は戦争に供出されたままであったのが平成四年(1992)、47年ぶりに再鋳されました。
七面堂は名前のとおり末法総鎮守の七面天女が祀られ、毎月19日の縁日には近隣の信者の参詣で賑わいます。また8月18日の宵宮、19日の大祭には他町村からの参詣もあり、以前は中里町の無形文化財で、当山が発祥の地である盆踊り「なにもささ」が境内でよく踊られました。

弘法寺に奉安されている大黒尊天は、日蓮聖人の御真刻と伝えられ、奥書には
「三浦妙達尼所納之 高祖御真作之大黒天壱合…永く當院に安置をしむ ―以下略― 天保十年三月智泉院日啓(花押)」
と、記されています。
そのお姿は、通常の「右手に小槌、左手で袋を担ぎ、俵に乗る。」ものと異なり、「両手で小槌、俵と並べた袋に乗り、右足を上げ、駆けている。」 福来のお姿です。その袋の絞り口には『日蓮』の刻字が見られます。