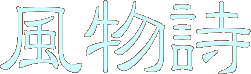
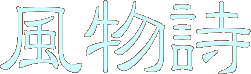
シンドリアは南国である。
一年を通して夏のような気候であり、当然。冬だって、常夏の気温である。
だが、冬なのである。
冬といえば、雪見酒。雪見酒といえば、温泉。そうなのだ、温泉の季節なのである。重ねて言うが、シンドリアは常夏なので、温泉で体の芯まで温まるなんてことはいらない。だが、温泉はある。あまり知られてはいないが、確かにあるのだ。シンドバッドお気に入りの温泉は、自分が心行くまで寛ぐために周囲にさえ内緒にしている。そこに浸かりに行くのは、夏でも冬でも嬉しい限りなのだが、そんなことを言ってしまえばこのお話は終わってしまうのでとにかく冬は温泉と決まっているとシンドバッドは、誰に言う訳でもないのに力説をした。
そう、温泉。温泉といったらあれだ。間違いなく裸の付き合いである。どこかの国では水着を着用の上で入浴するのが常識なのだそうだが、誰が何と言おうと温泉は裸である。
「流石に雪見酒は無理だとしても……」
ジャーファルが席を外していることをいいことに、シンドバッドは窓辺に寄って中庭を見下ろした。そこでは、仲良し三人組が楽しそうに笑っている。その一人。金色の髪の毛を持つ少年にシンドバッドの目が細くなる。いつ見ても、可愛い。可愛いという年齢ではとうにないのだが、何かどこか可愛らしい。
「アリババくんだけで酔えるな、うん。間違いない」
アリババと二人きりで、温泉。あの白い肌を惜しげもなく晒し、水が滴る髪の毛に、温泉で暖まって上気した頬。考えただけでも素晴らしい。アリババ見酒と、いうものがあってもいいのではないか。そうだ、そうしよう。
何勝手に決めているのだと方々からツッコミがきそうだが、シンドバッドは決意した。
(アリババ見酒をしよう)
揺るぎない決意と、思いついた事柄への賛辞を自分でしながら、シンドバッドは上機嫌で仕事にとりかかる。そうと決まれば早く終わらせるに限る。王様は、どうやってアリババ見酒をより有意義なものとするかばかりを考えながら、もはや修行に近い仕事を片付けていった。
幸い。自分を最初から尊敬しているらしいアリババを舌先三寸で連れ出すなんてことは簡単な事だった。連れ出してやって来たのは、シンドバッドの秘湯である。
「温泉っていうんですか?」
アリババは、温泉を知らなかった。
「そうだよ。このお湯には様々な効能がある。まずは、服を脱ぐんだ、アリババくん」
戸惑うアリババに先立つようにシンドバッドは豪快に服を脱ぎ捨てた。一応良心とばかりに腰にタオルを巻く。それから湯に浸かって、アリババを振り返った。
「アリババくんもおいで」
「あ、はい」
アリババは疑うことなく、服を脱ぎ、肌を露わにした。
大事なところだからもう一回言っておく。服を脱ぎ、肌を露わにし、腰にシンドバッドがしたようにタオルを巻いたらしく、物陰から出て来た時。少しだけ残念に思ったのは言うまでもない。アリババ限定でそんな良心は捨てて、さぁ身も心も解き放たれろ。と、言いたかったが誰かに見られては勿体ない。全てはいつか近い将来、寝所でじっくりしっかり見せてもらうことにする。と、シンドバッドは己に言い聞かせた。しかし、眼福である。色白のアリババの肌に日の光が当たり、白さをいっそう際立たせている。日焼けをしやすい砂漠気候の街に住んでいたと聞いたが、彼は日焼けをしない性質のようだった。更に陽光に照らされたアリババの髪はより美しく輝き、まさに天使。と、いう言葉がふさわしかった。
「し、失礼します」
いつのまにかアリババが、傍までやってきて湯に足を入れた。始めはおそるおそる、すぐに気持ちがいいものとわかったのだろう、肩まで浸かってふぅ。と、息を吐いた。
「気持ちがいいだろう?」
「はい」
アリババは嬉しそうに笑う。そんな彼の様子にシンドバッドも嬉しくなって笑った。
ふたりして、しばらく湯を堪能した。最初は何故か7緊張していたアリババであったが、次第にリラックスしてきて、シンドバッドの話にも快活に相槌をうち、硬くしていた身も少しずつほぐれてきたようだ。シンドバッドは、何食わぬ顔して、近寄って行った。
「ところでアリババくん」
「はい?」
アリババが小首を傾げた。水分を含んだ髪の毛が張り付いて、シンドバッドは興奮で軽く目眩を覚えた。
「裸の付き合いというものを知ってるかい?」
「は?」
何それ。と、あからさまに不審な顔をする。シンドバッドは、自分の下心を気取られぬように気をつけつつ、口を開く。もちろん、アリババに近寄っていくこともやめない。理想としては、裸の付き合いを力説しつつ、アリババの肩を抱くである。出来ればそのまま自分の上に坐らせてみたいのだが、それをやるとシンドバッドが大変なことになりそうだったので、自重するとしてもそこだけは。
「裸の付き合いをすることでより深く相手を理解できるという実にいいものだよ。アリババくんと俺が一緒に温泉に浸かっている。こんな風にただ並んでいるのもいいが、やはりこうやって……じっくりと話しこんだほうがより親密になれそうだと思わないか?」
「なっ、ちょ。シンドバッドさんっっ」
強引に肩を引き寄せた。アリババは水中でバランスを崩し、シンドバッドにもたれかかるような格好になった。
「どうした、水の中では深くなくても危ないぞ」
「危ないって、シンドバッドさんが引っ張るから……」
アリババが抗議の声をあげかけて、突然黙った。顔は真っ赤だ。さらに肌も少し赤みがさしているように見える。
どうしたのだ、急に。と、思ったが。自分と密着状態なのが恥ずかしいのだろうということにすぐに思い至った。
(すると、彼は俺を意識しているということになるか)
男同士、密着したところで意識していなければ気にならないかもしくは、嫌悪感しかない。だが、アリババは羞恥に頬を染め、身を硬くしている。
「引っ張るからなんだ?」
わざと低めの声で言うと、アリババはさらに顔を赤くした。
「……み……して」
「なんだ、聞こえないぞ?」
小さな声でモゴモゴといった言葉は、ちゃんとシンドバッドの耳に届いている。だが、恥ずかしがっているアリババが可愛くてシンドバッドは意地悪にも聞こえないふりをした。
「な、なんでもないです」
「そうか?」
シンドバッドはニコニコしたままアリババを引き寄せ、そのまま自分があとで大変なことになりそうだが、いいや。と、アリババをひょい。と、自分の太股の上にのせて、アリババの肩のあたりに顎を乗せた。
「う……あの、これ。何か間違ってません?」
「いや、立派な裸の付合いだ」
アリババの腹の前に手を回し、シンドバッドはアリババにバレぬようにアリババの髪にそっとキスをした。
(耳まで真っ赤だな。本当にかわいいよ)
このまま食べてしまいたいほどに。耳まで真っ赤なアリババは、シンドバッドに抱っこされたまま、ひたすら真っ赤な顔をして目を泳がせている。
「アリババくん、緊張しているのか?」
「い、いえっ。別にっ」
声が震えている。本当に、もう。どこまでかわいいのか。ニヤける顔を見られる心配もないから、シンドバッドはどこまでも顔を緩ませながら、アリババを少しだけ強く抱きしめた。密着した肌が、熱い。
「なぁ、アリババくん。君の心臓も俺の心臓もドキドキしている。これってどういうことだろうね」
アリババが、びくっ。と、した。
「君は、何故こんなに顔を赤くしているのかな?」
「それは―― 、」
「君は、どうして嫌がらないんだ?」
「ッッ」
アリババがモゴモゴと何かを言った。その言葉は、シンドバッドの耳にはきちんと届いていて、シンドバッドは嬉しくて口許を緩めた。
「アリババくん」
シンドバッドは再び、背後からきゅ。と、アリババを抱きしめた。シンドバッドの裸の胸とアリババの背中がぴったりとくっついた。アリババが息を飲んだ。
「いけないこと、しちゃおうか?」
「!」
温泉でその後何があったのか。それは、アリババとシンドバッドだけしか知らない。
(アリババ見酒。最高だった)
シンドバッドがアリババ見酒を再び目論むのはそう遠くない未来なことだけは確かなようであった。
終
2013.01.06.に行われた大阪シティで配布したペーパー小話です。
既にPixivの方にはアップ済みのものですが、サイトにも掲載します。
シン様酒飲んでませんが、アリババくん=お酒ってことで。
ここまで読んでくださってありがとうございました。
2013.01.22.サイト掲載