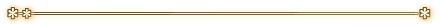

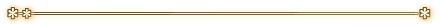
「愛してはいけない人」の劇中譚です。
|
「可愛いね」などと不用意に言うと、従弟は不機嫌になる。
そう思うから口にするだけなのだが、東谷の領主でありマークの騎士軍団長でもあるという強い自負を抱いているエオメルは、いつまでもセオドレドに子ども扱いされたくないらしい。
だが王子はつい、目の前の精悍な若い青年に、幼い頃のあどけない表情を重ねてしまうのだ。
あるとき、セオドレドは従弟が恋をしていることに気づいた。
いつ恋に落ちたかは知らない。
自分の知らぬ間に、秘めた思いを育てるくらいには大人になったんだな、と初めてエオメルの成長を実感した王子だった。
恋の相手はゴンドールの兄弟らしい。
「どっち?」
尋ねても従弟は答えなかった。
ただ俯いて少し頬を赤らめたくらいである。
そして王子に悟られてから、エオメルの視線は慎重になった。
かれは苦笑して相手の肩を抱き、「秘密主義だね」と囁いた。
胸の奥に湧く従弟への想いが、静かに高まっていくのを感じながら。
だが眩しそうにゴンドーリアンたちを見つめていた従弟の瞳に、いつからか憂いが沈んでいた。
屈託のない、憧れのまなざしは睫の影に伏せられるようになり、深まった瞳の色が王子に読めない感情を伝えている。
そして、ゴンドーリアンの方も。
エオメルは教えてくれないが、セオドレドにはわかった。
執政家の兄弟のうち、兄の方は感情を表に出すタイプだ。
何かあったならすぐに知れる。だから残る一人がエオメルの想い人だ。
セオドレドは注意深く観察した。
ファラミアが、いつもの穏やかな白皙の向こうに、焼けつくような渇望を抱えてエオメルを見ている。
二人がどうしたのかはわからない−−いや、起ったことならわかるが、それぞれの感情の経緯は知りようがない。
従弟と執政の次男は惹かれあいながら面と向かおうとはせず、互いに背を向けているときだけ、安んじて視線を送っている。
(でも教えない)
気づいているのは自分だけだ、とセオドレドは思った。
(ファラミアとは手強いな・・・)
エオメルが手綱を渡してしまえば、弟君は思いのままにロヒアリムを乗りこなすだろう。
だが今なら、作り上げてきた従兄弟同士の絆が自分に味方するはずだ。
「今夜は寒いな」
軍装を解いて王子は言った。
行軍中の天幕の中だった。
同じ陣地内にゴンドール軍も展開している。
「もっと毛皮を運ばせましょうか」
「いや、いい。酒が欲しい」
エオメルが酒壷を手渡した。それを受け取って呷る。
「あまり召し上がらないほうが。明日も早いですよ」
「飲み足りないくらいだ。酒宴では大して飲んでないんだから・・・きみはいつのまにかテントに帰ってしまうし」
「身体を休ませたかったので」
王子の衣服をたたみながらエオメルが答える。
「ボロミアとファラミアが残念がっていた。かれらもすぐにいなくなって盛り上がらなかったな。ゴンドールの兄弟はきみともっと話したかったそうだ」
相手を横目で見つつかれは言った。
従弟が瞬きし、そっとため息をついた。
「わたしはつまらぬ事しか言えません。公子たちの話し相手は殿下の方が相応しいでしょう」
「かれらはね、きみに好意を持っているんだよ」
甘い痛みに耐えるように眉を寄せ「そうですか」と言ってエオメルは立ち上がった。
小さなランタンに灯りをともすと、天幕の中に橙色が広がった。
だが吐く息は白く、毛皮にくるまっても冷気が忍び寄ってくる。
「本当に冷えますね」
「氷室のようだ」
王子が言うと、従弟が寝床に潜り込んできた。
すぐに互いの身体に腕を回し、抱き合って体温を感じあう。
騎士たちの間では通例の慣習だ。
それ以上の行為は双方の同意が必要だが。
「きみはあったかいね」
従弟の長い金髪に顔を埋めながらセオドレドが囁いた。
「あなたは指が冷たくて、わたしの方はいまいちです」
それを聞いて忍び笑う。
「じゃあ暖めてくれ」
衣服の中に手を這わせる。
引き締まった肌を撫で上げ胸の突起を探り当てた。
「あ」
セオドレドのひんやりした指先に摘まれて、エオメルが身を震わせる。
玉を転がすように弄びながら、時折強く潰しての圧迫を繰り返した。
「あぁっ、あっ、あっ」
甘い声を続けて洩らすと従弟は王子に下腹部を強く擦りつけて来た。
セオドレドの太腿に、固い熱い感触が当たる。
かれらは互いに下衣をずりおろして、肌を密着させた。
ペニスが触れ合う生々しさに息が乱れた。
王子はエオメルの腿から尻を撫で回して確かめた。
腰周りが充実して抱き応えがある。
「早く・・・」
じれったげに呟くと、従弟はかれの手をつかんで自分のものに導いた。
「今夜は素直だな」
ハッ、ハッと息を吐きあい、ロヒアリムたちは互いへの愛撫に熱中した。
甘い戦慄が背中を駆け上がり二人に固い勃起をもたらす。
エオメルは目を閉じて快感を貪っている。
まだ少年の頃に、良いことも悪いことも教えたセオドレドである。
だが大人になると、従弟はプライドが高く独立心の強い騎士に成長した。
あの日も、かれらはゴンドール軍と共に戦場にいた。
寝屋に誘うと「あなたを拒む理由がないのがいやだ」などと言われた。
「へえ?難しいことを考えるようになったんだね、この金色の頭は」
頭をなでようとしたが、身体をよじって逃げられた。
「嫌われてるとは知らなかったな」
「違います」
エオメルは強い目線でかれを見た。
「あなたは他の者とは違う。わたしはあなたに逆らえない。支配されてしまう・・・」
セオドレドは秀麗な顔に笑みを浮かべて尋ねた。
「それは、そんなに悪いことか?」
従弟は答えられずに黙ってしまった。
それを強引に抱き寄せて唇を合わせる。
若い体は、いつも燃え立つきっかけを捜しているものだし、ロヒアリムはさほど禁欲的ではない。
抱きしめてしまえばエオメルは拒まなかった。
そしてかれらは愛撫を交わしあったのだが、確かに、親しすぎる相手と肌を合わせるのは気まずいものかも、と感じたセオドレドだった。
以来、あまり二人で何かする機会を作らなくなった。
それに従弟に逆らわれると、それがささやかなものでも気分が悪くなるから、というのもあった。
でもその時はまだ、エオメルが誰かを愛していることには気づかなかったのだ。
「ぁあ・・・っ」
擦りあげる指の動きを強めると、従弟は首を仰け反らせて身悶えた。
「随分感じてるじゃないか」
「久しぶりだから・・・あ、あなただってこんなに」
声が艶めかしく濡れている。
しばらく触れずにいたあいだに、従弟の背中はさらにしなやかな筋肉に覆われていた。
手ごたえのある体が好ましい。
張りつめた性器を弄りながら王子はもう片方の指を、尻の奥に這わせた。
「あッ!」
ぐっと押して刺激する。
従弟が声を上げた。
−−ここはまだ試したことがない。でも今夜は・・・。
入れるか入れないかの強さの指先で、襞を刺激するとエオメルのペニスがびくんと揺れた。
「で、殿下、ああっ」
従弟がよがっている。
以前は触れただけで嫌がったのに。
そんなところをと抗議され、かわりに口に咥えさせたことがある。
それも不満そうだったが命令だよといってねじ伏せたのだ。
なのに、尻ですごく感じるようになっている。
(誰に教えられたか白状させてやるからな)
王子は二本揃えて突き刺した。
「うっ・・・!」
悲鳴を上げそうになるのを、唇を塞いで封じてしまう。
するとエオメルのほうから激しく舌を絡めてきた。
もともと従弟はキスが好きで、覚えも良かった。
舌を甘く噛みあい、強く吸いあって唾液を混ぜ、くちゅくちゅ音を響かせる。
内部に埋めた指は狭い壁を押し広げながら、抉りまわしていた。
「ああ・・・セオドレド・・・」
唇をはがし、指も抜くとエオメルは涙目で王子を見上げた。
「どうして欲しい?」
冷静に尋ねる。
「じらさないで下さい」
セオドレドも欲しくて堪らなかった。
でも自分から求めるのは嫌なのだ。
エオメルが唇をかみ、その腕が王子の首に回された。
「−−あなたのもので、わたしを貫いて欲しい」
「もっと開くんだ」
大きく広げ、膝を立たせる。
その足の間にセオドレドの腰が覆いかぶさった。
「あ、あ、あ・・・!」
熱い、硬い肉棒がエオメルの秘所にめり込んでいく。
「ひぃッ!い、痛い、ああッ」
悲鳴を上げる唇に指をあてて王子は言った。
「エオメル、声は密やかに」
「で、でも、あう・・・!」
「もう少しで全部入る」
ずり上がろうとする肩を押さえて腰を突き出すと、根元まで貫通出来た。
「あぁ・・・んっ」
普段の精悍な表情からは想像できない淫らな声で、従弟が乱れる。
散らばる金髪がなまめかしい。
「ぴったりじゃないか?」
セオドレドは呼吸を整えながら呟いた。
強い締め付けを味わって満足の吐息をもらす。
「うぅ。でも、痛い・・・」
「少し馴染ませようか」
そう言って腰を押し上げる。
エオメルが息を呑んだが、セオドレドは苦痛を与えぬよう慎重に動いた。
「あ・・・」
ゆっくり、徐々に馴らしていく。
内臓を拡げられる感触が、エオメルの下半身を痺れさせた。
熱いペニスを埋め込みながら、腰の動きと連動して王子は従弟のものを扱きあげた。
「あぁッ・・・すごい、いい・・・」
先端をぐりぐりいじり、指で強弱をつけて摩擦する。
「あぁんっ、溶けてしまうっ」
エオメルのペニスは脈打ち、露があふれでた。
「い、いきそうだッ」
激しく身を仰け反らして喘ぐのを、かれは指で押さえて阻んだ。
「おい、きみは一人で愉しみすぎだ」
「いやだ、あぁッ、我慢できない」
「わがままは許さないからね」
「いかせてください!でないと、変になりそうだ」
セオドレドはふん、と鼻で笑い、従弟に顔を近づけて言った。
「ならファラミアとのことを白状しろよ」
「な、なんです」
一瞬エオメルの身体が強張る。
「わかるんだよ。ここを」
ぐい、と深くえぐって「ひっ」と呻かせる。
「かれに使わせたんだろう。すっかり開発されてるじゃないか。まあ、まだかなり狭いが」
エオメルは顔を背けて眉根を寄せた。
「そんなこと、あなたに言う必要はありません」
「へえ。そう?素直じゃない子には優しく出来ないな」
そう言うと、セオドレドは一気に腰を突き上げた。
「ああーーーッッ!」
甲高い悲鳴を聞きながら、激しいピストンを繰り返す。
「駄目ッ、痛い!裂けるッ」
「散々やったんだろ」
大きく揺すり上げられ、エオメルは王子にしがみついて叫んだ。
「いやだ、あぁっ、許してください・・・!」
「正直になれば許してあげる。ファラミアと何度寝たんだ?」
「それは−−い、一度。一度だけです」
「いつのことだ」
「去年、国境沿いで・・・あなたも、ボロミア殿もいなかったから」
「わたしのいない間にこの身体を開いたのか」
「・・・はい」
セオドレドは口元を歪め、意地の悪い声音で従弟に告げた。
「そんな悪い子には、もっとお仕置きしてやらなくちゃな」
エオメルの泣き声がうるさいので布を口につっこんで黙らせた。
広げた身体を串刺しにして貪る。
何度も突き上げるうちに、後腔が強烈な摩擦運動に熱く潤い、セオドレドのペニスを喜ばせた。
犯されながらエオメルのものも固く勃起している。
一度達しただけでは足りず、数回王子の腹に白濁を撒き散らしていた。
天幕の外から、微かに鳥の声が聞こえてきた。
空が白むのもじきだろう。
「こういうときは夜が過ぎるのが早い」
セオドレドは呟いた。
眼下の従弟は、桃色に染めた肌を波打たせて悶えている。
一際強く突き上げると、かれはやや抜き加減にして中に欲望を注ぎ込んだ。
「くぅ・・・っ!」
呻き声をあげてエオメルが熱い迸りを受け止める。
そして身を震わせながら、自らも幾度目かの絶頂に達したのだった。
「もう。大嫌いだ。オークに襲われてどうにでもなればいいんだ」
朝の光の中で、従弟がぶんむくれて王子を罵っていた。
知らぬふりで顔を洗うセオドレドである。
「徹夜になってしまったな。本当にオークが出ても剣を握る力が入らなさそうだ」
着替えながら言うと、エオメルはそっぽを向いたまま答えた。
「わたしは助けないから」
ふふ、と王子が口元で笑う。
「ほら、マントを忘れているぞ」
天幕を出る前に、着せかけるふりをしてそのまま抱きしめた。
「触らないで下さいッ!」
「おお怖い」
もがく身体を抱きながら、セオドレドは耳元に囁きかけた。
「きみのことなら、何でも知りたいんだよ」
「迷惑です!」
「そんなこと言うな」
耳朶をきゅっと噛んで舌を這わせると、腕の中の相手はびくりと震えた。
まだ身体の中に、与えられた快楽が残っているのだ。
「最近一人で秘密をかかえてひどいよ。きみが遠くに行ってしまうようで、嫌なんだ」
「わたしはどこにも行きません」
身体から力を抜いてエオメルが言う。
「あなたこそ・・・」
「なんだい?」
従弟は首を振り向けて王子を見つめた。
「殿下のほうがずっと狡い。わたしのことを何もかも知ってしまうくせに、自分の心のうちは明かさない」
その声は子どものように不安げだった。
ふいにセオドレドは見つけた。
相手の瞳の中に、かれの心の奥にあるのと同じ想いがひそんでいることを・・・。
ローハンの王子に、甘美な目眩が訪れる。
従弟は気づいているのだろうか。
いや、それは気づく必要もないことだ。
他に誰を愛そうと、かれらは生まれたときから、互いのものだと決められているのだから。
「セオドレド」
エオメルが王子の名を呼ぶ。
その響きは苛立ちながら甘えていた。
「あなたは、何のつもりであんなことを」
問いかける表情が真剣だった。
ここで愛の言葉を告げたなら、従弟は堕ちて、かれの足元に跪くだろう。
教えないよ、とセオドレドは決めた。
そのほうが長く楽しめそうだから。
(きみに恋してるなんて言わない。でも恋してないと言ったら偽りになる)
だから、結局こう言うしかないのだった。
「きみは可愛いね」
20070107up
甘々を予定してたのに無理姦て。なんでか。病気か。
こういうのが好きでどうしようもありません〜今年もよろしくです。
|
|