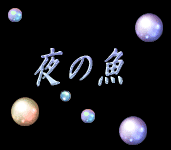
this current flows into my dearest. |

|

ローハンの騎士エオメルは夜空を見上げた。
かれは今夜も愛馬を駆りたててマークの荒野を走り抜けるつもりだ。
空に瞬く星の輝きに従えば、夜の闇に惑わされることなく目的地までたどり着けるだろう。
長身を馬上に据えると、かれは馬の腹を蹴った。
そしてセオドレドが待つ西エムネトに向かって駆け出した。

十七歳になったエオメルは、王子セオドレド率いるオーク征伐隊の長期遠征に初めて参加を許された。
エオムンドの息子は常に敵の正面に切り込んで剣をふるい、恐れを知らぬ戦いぶりでかなりの成果をあげたので、古参の騎士たちにも感心された。
だがまだ若いかれは、戦闘が終わってもなかなか平常心を取り戻すことが出来ず、震えの止まらない腕と高揚したままの心をもてあましていた。
掃討戦が終了し、明日はエドラスに帰還するという夜のことである。
エオメルはそっとセオドレドの天幕を訪れた。
「セオドレド・・・」
相手の名を呼びながら、半ば眠っていたらしい従兄の寝床に潜り込んで頬を触れ合わせる。
セオドレドは目を見開いてエオメルを見た。
「なんだ、こんな時間に」
「・・・今夜は一緒にいて欲しいんです」
従兄の首筋に唇をあて、相手の衣服の下に手のひらを滑り込ませながら、エオメルは囁いた。
数ヶ月前から、従兄弟同士は一線を越えて愛を交わす仲になっている。
「遠征に来てからずっと、わたしは身をわきまえてあなたに甘えないようにしてきました・・・王子の従弟ではなく、ただの騎士の一人として振舞いました。でももう行軍は終わりだし、あなたに触れてもいいでしょう?」
下着の中に這いこもうとしたエオメルの指を、王子はぎゅっと握って阻止した。
「明日にはエドラスに帰るんだ。そうしたらいくらでも機会がある」
「でも、ずっと我慢していたんです・・・今すぐ、いつもみたいにして下さい」
セオドレドが瞳を細めて「いつもみたいにってどういうのだったかな」と言うと、エオメルは可愛い顔をふくらませて相手をにらんだ。
「夜、あまり眠れなくて・・・あなたのことばかり考えていた」
王子の首にすがりつき、相手の髪をかき乱しながらエオメルは呟いた。
「初めて最前線で実戦を経験したんだ、気が高ぶっているんだろう」
軽く肌を撫でただけで激しく喘ぐ従弟を、力強い腕で抱きしめながらセオドレドが尋ねる。
「ウェストにこんなに腕が回るよ。随分やせたようだね、エオメル?」
「−−戦いの後だと、何か食べようとしても指が震えて、肉を落としてしまうんです。それにあまり腹が減らないし」
「食べないといきなり倒れるぞ。じゃ、こんな余計なことで体力を消耗するのはまずいんじゃないか」
そう言ってわざと身体を離そうとする従兄を、かれは背中に腕を回して引き留めた。
「いやだ。なんでそんなに意地悪なんだろう」
エオメルの涙目の抗議に、セオドレドは笑い声をあげてかれの額に口づけた。
「あっ、はあッ、んぅッ」
性器を握って強く擦りあげられると、従弟が王子の腕の中で身悶える。
手の中の物はすぐに先端から露をこぼして、セオドレドの指を濡らしはじめた。
「大きな声を出すと聞こえるぞ。すぐ外に歩哨がいる」
「だって・・・ああ−−くッ、ふッ」
エオメルは必死に声を出すまいと唇を閉じようとした。だが、指の刺激に耐えられず押さえきれない喘ぎが洩れてしまう。
顔を真っ赤にして感じている従弟の様子に、セオドレドも身体の芯が疼いて熱くなる。
「どうする。ここでは、これ以上はちょっと・・・天幕の布の向こうにはまだ騎士たちがうろうろしているだろうし」
「や・・・やめちゃイヤだ、あッ、もっと続けてください」
「続けたっていいけどね。でもきみは」
指の動きを強めながら、王子はもう片方の手でエオメルの尻の奥をぐっと押した。
「ひッ、あんっ」
「・・・こっちにも欲しいんだろう?」
低い声で問われたかれは、金髪を振って頷いた。
「は、はいッ、ああセオドレド、早く・・・!」
「だからそれはまずいんだよ。きみはあの時の声が大きいから、そこら中に響き渡ってみんなに聞かれてしまう」
「そっそんなこと、知りませんッ」
エオメルは耳まで赤くして羞恥に身をよじった。
「今夜のところはこうやって、きみを指で可愛がればいいかと思ったけど−−わたしのほうも我慢できなくなってきたようだ。いったん止めるよ」
セオドレドはそう言うなりかれの身体から身を起こした。
「あ・・・」
まだよく意味がわからぬエオメルは、離れた従兄を求めて腕を伸ばした。
「場所を変えよう。そのくらいは我慢できるだろう?−−邪魔の入らないところで、欲しいだけあげるから。いいね?」
王子は相手を見下ろして言った。
そしてかれの性器を愛撫して濡れた指を、エオメルの唇に突き入れる。
−−横たわったままの従弟は、瞳を潤ませてセオドレドの白い指に舌を絡ませた。
「眠れないので風に当たってくる」
そう警備の歩哨たちに告げると、セオドレドとエオメルは天幕を出た。
しばらく歩いていくと、エオメルが「水音がします」と従兄に言った。
「エント川だろう。この先はもうファンゴルンの森だ」
振り返ると野営地の焚き木のともし火が、ごく小さくなっていた。
セオドレドは夜の闇に耳を澄ませた。
「この辺でいいだろう・・・わたしたちの他に誰かいる気配は感じない」
エントの川岸に王子が羽織ってきた厚いマントを広げると、ロヒアリムたちは衣服を脱ぎ捨ててその上に転がった。
エオメルの足を大きく広げさせたセオドレドが、いささか乱暴に従弟の秘部に指を押し込んで中をえぐりつつ、「まだ、どこにオークが潜んでいるかもわからないのに、こんな所で快楽に耽ろうというんだから・・・大馬鹿だなわたしたちは」と慨嘆した。
するとエオメルは傍らに放り出してあった愛剣グースヴィネをつかんで引き寄せた。
そして王子の愛撫に吐息を漏らしながらも、「もし、敵があらわれたら、わたしがあなたをお守りします」と告げたのだった。
「−−エオメル」
セオドレドはその言葉にひどく胸を揺さぶられた。
瞳に星の光を映した従弟に見上げられ、「セオドレド、わたしはちゃんと戦えたでしょう?戦場であなたの役に立ったでしょう?」と問われると、ローハンの王子は微笑んだ。
そして「ああ。きみはマーク一の勇者だよ」と心から囁いた。
指でほぐした部分にセオドレドの張りつめたペニスが押し当てられると、エオメルは息をつめて王子の腕にすがりついた。
一突きごとに、敏感な肉を掻き分けて固い感触が侵入してくる。
拡げられて皮膚が引き攣る、異様な生々しい感触にのけぞって天を仰ぐと、空には銀河が筋を作って瞬いていた。
「アッ、アッ、はうッ、セオドレドッ」
かれの足を抱えあげ、態勢を整えた従兄が強引な突き上げを開始する。
「んぁッ、ま、待って、痛いッ、あッあぁッ」
「すごくいいよエオメル、狭くて・・・絡みついてくる」
「あっ、うぁッ、ひッ」
野外での行為にそそられたせいか、セオドレドはいつもより激しく揺すりあげた。
まだあまり情事に慣れていないエオメルの身体が、苦痛を訴えて軋む。
「い、痛いですッ、もっと、優しく」
「そう?きみの中は随分ぬるぬるして、悦んでいる様だけど」
素っ気無い口調で答えて、従兄は責め苦を続けた。
興が乗ってくると、どんなに泣いて嫌がっても、セオドレドは手加減などしてくれないことをエオメルは今までの経験でわかっていた。
「う−−く・・・っ」
かれは唇を噛締めて相手の動きに身を任せ、敷かれたマントを握りしめた。
「あー・・・あはぁッ、んっ、あ、あぁんッ」
根元まで挿入された物に、内壁を掻きこすられてえぐり回されると、自分でも信じられないような声が喉から迸る。
自分が快楽によがっているのか、苦痛にあえいでいるのかもよく解らない。
でもエオメルにとっては、そのどちらでもかまわなかった。
セオドレドになら−−何をされても許してしまうことを、かれは知っていた。
従兄のたくましい体の下で悲鳴を引き出されていたエオメルが、急に相手にしがみついて尋ねる。
「わ、わたしの声は大きすぎて−−うるさいですか。拳を口に入れて、我慢した方がいい、のでしょうか?」
それを聞いた王子はかれの瞳を見つめてクスクス笑った。
「いいや。きみのあえぎは素敵だよ。誰よりも淫らで・・・わたしを酔わせる。もっといい声で鳴いて欲しいものだね」
そう言うなり、更に深く腰を押しつけて、エオメルを「あぁっ」としならせる。
突き込まれ続けて、全身がのたうち、脊髄を戦慄が駆け上がる。
そしてふと横を向いたとき、エオメルの快楽に霞んだ視界に、川面に何かが跳ね上がってぽちゃん、と落ちるのが見えた。
行為の終わったあと、余韻にびくびくと身体を痙攣させる従弟を、「まるで陸に上がった魚みたいだな」とセオドレドが評した。
「そういえば、さっき魚が跳ねるのを見ました・・・あ、ほらまた」
細身の魚が水面に飛び上がり、銀色のうろこが光る。
息を整えながらエオメルがそう言うと、王子は「なんだ、夢中でよがってると思ったのに、魚なんか見る余裕があったのか」とちょっと不機嫌な口調で呟いた。
エオメルは慌てて従兄の肩に手を置いた。
「ち、違います、たまたま目に入っただけで」
そして相手の腕を取り、指を絡ませた。
「・・・わたしの中をあなたに一杯にされて、他の事など何も考えられなくなっていました」
かれが頬を赤らめてそう言うと、セオドレドはかれを抱き寄せて「知ってるよ」と囁いた。

二十歳を過ぎ、軍団長に任命されると、エオメルは名実ともに父の後を継いで東谷の領主の地位を確立した。
だが、地位を得たことで、セオドレドと過ごす時間は少なくなった。
従兄に一人前の騎士として認められたい、王子の役に立ちたい−−という願いは叶ったが、エオメルを信頼したセオドレドが従弟にエドラスの守りを任せて、自分は国境の守護に出撃することが多くなったのである。
時たま黄金館に帰還するセオドレドを、エオメルは待ち続けた。
−−ある年の春、半年ぶりに帰ってきた従兄は、エオメルとの空白の時間を埋める間もなく、二日ほど滞在しただけですぐ出立してしまったのだった。
エオメルは、セオドレドの軍列が遠ざかって行くのを、やるせない思いで見送った。
そして、もう待つだけの日々には飽きた、と心の中で呟いていた。
その日のローハン軍の野営地は、西マークの湖畔に設えられていた。
夜が更けた頃、エオメルは王子の寝所に忍び込んで従兄を驚かせた。
「エオメル!何故ここにいるんだ−−いつ来たんだ」
「たった今です。あなたに会いたくて、荒野を駆けてきました」
セオドレドの髪に顔を埋めてかれは熱く囁いた。
「待つのは嫌になりました!あなたが欲しくなった時には、自分から奪いに来ることに決めたんです」
情熱的にそう告げて、エオメルは王子の腕をつかんで引っ張った。
「行きましょう、二人だけになれるところへ−−昔、わたしが初めてあなたと行軍を共にしたあの夜のように」
それから幾たびも、エオメルは従兄を求めて夜の中を駆け抜けた。
会う毎にかれらは次の約束を交わしあい、逢瀬は月に一度ほど行われるようになった。
エオメルは空を見上げ、星の位置で方角を測りながら王子のもとを訪れた。
月明りの下のマークの荒れ野は、決して安全な道筋ではなかったが、セオドレドの腕に抱きしめてもらえるなら何も怖くなかった。

だがその夜は違っていた−−エオメルは、初めて道に迷ってしまったのである。
岩場のあいだで、かれは途方にくれた。
その日は、夕方はまだ晴れて夕陽が輝いていたのに、陽が沈むにつれて厚く雲が垂れ込め、空を覆って月と星を隠してしまったのだった。
エオメルは馬をおいて岩場の上に登ってみた。
場所は西エムネトの中央から北寄りに位置しているはずだったが、見渡そうにも辺りは完全な闇に閉ざされている。
−−今夜は会えないかも知れない・・・。
かれは冷たい岩に腰掛けてため息をついた。
−−セオドレドは、わたしを待って心配しているだろうか。それとも、戦いに疲れて寝てしまったか。
わたしは王子を愛しすぎている、と闇の中でエオメルは思った。
−−マークを横断するのも厭わぬほどわたしはセオドレドを欲しているが、かれがどう思っているのかはわからない・・・。
暗闇が不安に形を変えて、エオメルの心を揺さぶる。
−−わたしは誇り高いマークの騎士だ。だが、自分でも信じられないくらい、セオドレドには全てを許してその要求に従ってきた。それは自分で求めたことでもあったのに・・・今、わたしは浅ましく見返りを欲している。そしてエドラスに背を向けて、荒野を彷徨っている・・・。
岩場の上に座ったまま、マントで覆った身体を寒風にさらしていたエオメルは、不意に空の一点が明るくなったことに気づいた。
雲の切れ目に、霞んだ月が姿を現していた。
「あ・・・」
風と共に雲が動き、西エムネトの荒れた地肌を月光が照らす。
その時、エオメルは遠くに光る波の飛沫を見つけた。
−−あれは、エント川だ。あの川に沿って西に向った所に、セオドレドがいるはずだ。
エオメルは岩場を駆け下りると、馬を引き、川に向って駆けていった。
水の匂いが強くなり、やがてかれの目前に黒い水流が現れた。
愛馬を駆りながら、かれは思い出していた。
−−昔、セオドレドと二人で、夜が明けるまでこの川を見ていたことがある。時々魚が跳ねて、川底にはいくつも銀鱗が光っていた。殿下は、「川を遡っているようだね。生まれた場所に戻るんだろう、傷だらけになって・・・。魚は何年大海で過ごしても、帰る場所を忘れないものだ」と言っていた。
そしてエントの流れは、今夜、わたしをあなたの元に導いてくれるようです、とエオメルは思った。
−−この川は、わたしが辿り着くべき唯一の場所につながっている。
月は朧に、星は隠れていたが、水面は数年前の夜と同じようにきらめいて見えた。
「エオメル・・・!」
王子の陣地が灯す明かりが微かに見えてきたとき、闇の中で聞きなれた声がかれの名を呼んだ。
エオメルは手綱を引いて馬を御した。
「殿下」
「良かった、随分遅いから心配したぞ」
かれが馬を下りると、かけよって来た従兄に抱きしめられた。
「わたしを待っていてくださったのですか・・・?」
「きみがなかなか来ないから、途中でオークに襲われでもしたのかと思って、気が気じゃなかった。陣地を抜け出して林の中を歩いていたのだが・・・東のほうから馬の足音が聞こえた気がして走ってきたら、きみがいた」
セオドレドは従弟の感触を確かめるように身体中を撫でさすり、何度もかれの頬に口づけた。
「きみに会うのが、月に一度じゃ少なすぎるくらいなのに、今日はもう来ないのかと思って絶望していたよ。今夜は星もなくて真っ暗だし−−そのせいで色々余計なことを思いつくし−−きみがエドラスで新しい恋人を作って、わたしを忘れてしまったんじゃないかとか」
「そんなこと、あり得ません」
エオメルは驚いて声をあげた。
「わたしがどんなにあなたを愛しているか、ご存知のはずだ」
「知っているけど、わたしは嫉妬深いんだ。きみは魅力的だから、離れていると色々考えてしまって・・・普段あまり考え事なんかしないので頭が痛いよ」
そう言ってセオドレドは腕の中の恋人をさらにきつく抱いた。
エオメルは甘美な想いに満たされながら、王子の肩に頭をこすりつけていた。
「もうすぐ夜が明けてしまいますね・・・あまり時間がありませんが、どうします・・・?」
川のほとりで、従兄と唇を交わしながらエオメルが尋ねると、王子は「するに決まってるだろう」と強く言った。
「わたしを心配させたお仕置きをしてやるからな」
「えっ、こ、怖いなあ」
セオドレドに下着ごと下衣を引きおろされ、エオメルはその場に這うよう命じられた。
うっすらと白んできた空の下で恥ずかしい格好をさせられ、かれの肌が羞恥に高揚する。
慌しく自分も前をはぐりながら、セオドレドは膝を突いてエオメルの双丘に顔を寄せた。
そして舌で従弟の秘所を舐めあげた。
「あぁッ、殿下・・・!?」
湿った感触に、エオメルの身体がびくんと震える。
「いけない、駄目です・・・そんなところをあなたが・・・」
舌先でこじ開けるように刺激され、かれは涙を浮かべて訴えた。
振り向こうとした身体はセオドレドに押さえつけられた。
「かまわない」
「で、でも」
「きみの身体はどこも素敵だよ。不思議だな、世界には人が溢れているというのに、わたしが欲しいのはきみだけだ・・・」
「−−ああ、セオドレド・・・」
同じです、わたしも・・・と胸を熱くしてエオメルが言おうとした時、逞しい感触がかれの中に侵入してきた。
「あっ、あぁぁっ!」
背後から容赦なく捻じ込まれ、エオメルが火のような息を吐く。
「くぅッ、殿下ァッ、いきなり深すぎます・・・!」
セオドレドは自分でも痛いぐらいに突き上げ、「お仕置きだって言っただろ」とかれに囁いた。
口調は冷静だったが、王子自身も昂ぶりの極致に達している。
従弟を貫きながら、エオメルの振り乱れる金色の髪は、やがて昇る朝日よりも輝いている・・・とローハンの王子は思った。
「あ・・・あ・・・あッ、セ、セオドレドッ、はぁッ」
艶めいた声でエオメルは喘ぎ、のけぞって悶えた。
セオドレドがもたらす狂おしい嵐に翻弄されながら、エオメルはまた、水面に銀鱗が跳ね上がるのを見たような気がした。
20050613up
世界は二人のために〜
セオドレドのことが好き好き大好きぃ〜なメルっちでありますv
|
|