ミルクandハニー
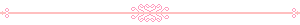
you know, take care not to be deceived by
Faramir’s honeyed face.
|
その日、東谷のアルドブルグ館に意外な客が訪れた。
館の主人である騎士国の軍団長エオメルは、部下からの知らせを受けて客人を出迎えに城門に向かった。
門のところには、金色の巻き毛のゴンドーリアンが一人、馬の手綱を引いて立っていた。
「ようこそ、ファラミア殿」
「エオメル殿、ですね。以前国境近くでのオークとの戦闘の際に、お姿を見かけたことがあります。今日はいきなり押し掛けて申し訳ない」
エオメルは、ごく軽装でしかも一人きりの相手を不思議そうに見て言った。
「執政家の公子にご来館頂けるとは、大変名誉に思います。それにしても、ここまでお一人でいらしたのですか?」
ファラミアは手綱の先の馬を困惑したように見て、ロヒアリムの質問に答えた。
「いや、実はわたしはこの数日、エント川周辺の警備にあたっていたのです。するとこの馬が、妙に落ち着かない様子でいると思ったら、今日わたしを乗せたまま突然走り出して、まったく制御できぬままこの東谷に駆けて来てしまったのですよ」
「ははあ、この馬があなたを乗せて勝手にここに?」
「そうです。こんなことは初めてです」
エオメルは馬に近づいて、安心させるようにその首を撫でた。すると馬はかれに応えて低い嘶きを返した。
「ああ、これはわたしがこの館の厩舎で育ててゴンドールに献上した馬ですね」
かれがそう言うと、ファラミアは不思議そうに馬を見ながら「そうなのですか・・・急に生まれ故郷に帰りたくなったということでしょうか」と尋ねた。
「かも知れません。孕んでいるようですから、ここで子供を生みたいのでしょう」
それを聞いたゴンドーリアンは驚きの声をあげた。
「この馬は妊娠しているのですか!?」
「そのようです。ファラミア殿には代わりの馬を差し上げますから、この母馬は置いて行って下さい。無事に仔馬が生まれたら、母子ともどもゴンドールにお返ししますよ」
そう言ってエオメルはにっこり笑った。
すぐに日が暮れてきたので、ファラミアは東谷で一夜を過ごすことにした。
食事を済ませたあと、二人はエオメルの私室でローハンの強い酒を飲み交わしていた。
強い絆で結ばれた友邦であるゴンドールとローハンは、共同で軍事行動を行うことが多い。
かれらは互いに何度か顔を合わせた事があるのだが、親しく話をするのはこの日が初めてだった。
今までエオメルのほうが年下であることや身分の違いをはばかって、執政家の子弟たちに馴れ馴れしくしないよう心がけていたのである。
だがかれは密かに、執政家の美貌で勇猛な兄弟たちに憧れの気持ちを抱いていた。
「いや、お恥ずかしい。わたしは自分の馬が牝馬ということすら知りませんでした」
ファラミアが酒杯をもてあそびながらそう言うのを、エオメルはにこにこしながら聞いていた。
かれは執政家の弟君と会話する機会を持てたことが嬉しかった。
「実際、ミナス・ティリスで仔馬が生まれても、わたしにはそういう知識がないので何の役にも立たないでしょう。安心して子供が育てられるように、あの馬は自分から故郷に戻ってきたのですね」
「我々の特技は馬の飼育くらいしかありませんから。ゴンドールの貴い方々の手は、馬を育てるようには出来ていませんよ」
ほろ酔いのエオメルは、そう言って手を伸ばすとファラミアの白い手をぎゅっと握った。
「ほら、ファラミア殿だってこんなに細い指をしているんだし・・・」
執政家の弟君は、自分の手に重ねられたエオメルの陽に焼けた指を目を見開いて見つめた。そしてそっと握り返したのだった。
「−−もっと早くから、あなたとこんな風に話がしたかったな。エオメル殿は偽りのない良い方ですね」
ファラミアの好意の表明に、純朴なエオメルは顔を赤くした。
「いやもう、わたしなぞは不調法な田舎者ですので、どう受け答えしたらよいかも分かりません。ですがそのように言っていただけると嬉しいです」
青い瞳のゴンドーリアンがそう言うかれを見つめて微笑んでいた。
そしてエオメルの手を口元に持って行きながら「あなたの指は、ローハンの太陽と草原を渡る乾いた風の匂いがしますね」と言って、口づけた。
ファラミアの唇が触れると、エオメルは驚いてどきまぎした。
そしてこういうのがゴンドール風の洗練された行為なんだろうか、と思っておとなしくしていた。
が、相手はいつまでもかれの手を握り締めたままである。
エオメルは控えめな声で「あの・・・そろそろ離して下さい・・・」と言ってみた。
ロヒアリムの手を頬に当てながら、弟君は「ずっと握っていたいな」と呟いた。
「はあ、こんな無骨な指をですか」
エオメルの戸惑った様子に、ファラミアがやっと手を離した。
そして湖のように澄んだ瞳でかれを見ながら「指にさわられるのがお嫌なら、代わりに他の場所に触れてもいいですか」などと言うのだった。
「他の場所といいますと・・・」
「唇とか」
かれの言葉にエオメルが仰天したので、弟君はくすくす笑った。
「からかわないでください」
エオメルがちょっと憮然とした顔になる。
ファラミアは「からかってなんかいませんよ」と言いながら席を立つと、テーブルを回ってかれの側にやってきた。そして青い目でかれを覗き込んだ。
「・・・なぜこっちに来るんですか」
思わず椅子の上で身体を反らしてしまうエオメルだった。
「嫌なら突き飛ばしてくださって結構です」
弟君の白い指がかれの顔にかかって、あっ、と思ううちに唇が重ねられた。
唇は軽く触れただけですぐ離れたが、ファラミアはエオメルの肩をしっかり抱くと、かれの身体を引き上げるようにして卓上に押し倒した。
酒杯が倒れて、床に落ちる音がした。
「ちょっと、待ってください。何をなさるのか」
テーブルに押し付けられながらエオメルはもがいた。
笑いを含んだ声でファラミアが言う。
「あなたがわたしを誘惑するからですよ」
「し、してませんそんなこと」
「したじゃないですか。手なんか握ってきて」
「そんなつもりでは」
ファラミアは優男のわりにかなり力が強かった。
力づくで押しのけることは出来るだろうが、執政家の貴公子を突き退けてもし怪我でもさせたら・・・とついエオメルは躊躇した。
するとまた相手の顔が近づいてきて、もう一度唇を奪われる。
−−な、なんだかいい香りがする・・・。
ファラミアの髪から漂ってくる良い匂いを感じながら、あまり現実感がなくエオメルは相手の舌が自分の口内を探るのを許していた。
許しているうちに、弟君はテキパキとかれの上着をはだけてズボンを引き下ろし、ハッと気づいたときにはほぼ全裸と言っていい姿にされてしまっているマークの軍団長であった。
「なっ何をするんです!止めてください」
素肌に手を這わせられて、我に返ったエオメルが身をくねらせる。
ファラミアはかれの腕を押さえてテーブルにはりつけにしながら青い瞳を細めた。
「あなたは駆け引きがお上手だ。たいした抵抗もせずにいると思うと、急にいやがったりして。そういう誘い方はわたしも嫌いじゃないですよ」
「違います、そんな」
そう言いながら、中つ国一の名門の子息に見つめられ、その美しい顔に覗き込まれるのが物凄くイヤ、という訳でもないエオメルだった。
ファラミアの綺麗な顔を押しのけて拒むのは、相手に悪いような気がした。
こんな高貴な美青年と愛撫を交し合うのは、生まれてはじめてのことだし・・・。
などと思い惑っているうちに白い指で乳首をつままれ、擦りあわされる。
「あぁッ」
エオメルの身体がびくんとうねった。
「感じやすいんですね」
さらに指の腹でくりくりとこね回されると、「あっんっ、んんッ」と甘い声をあげて身悶えてしまう。
「いい声を出しますねえ。ああ、こっちも相当はしたないことになってますよ」
勃ちあがりかけたエオメルのものを弟君がキュッと握ると、瞬時にそれは完全に勃起した。
「あッ、ファラミア殿・・・!」
「これが噂に聞くロヒアリムのキャノン砲ですか、凄いですね」
ファラミアが感心した声を出しながら乳首と性器を同時に撫でさする。エオメルは相手の首に手を回してすがりながら、あっ、んっ、はっ、うっ、いっ、などと喘いでいた。
「艶々してるし、手触りもいい・・・」
先端から液体を洩らし始めたエオメルのものをさらに激しく擦り上げつつ、ファラミアがかれの片足を抱えあげた。
尻の谷間の色づいた秘所が見える。締まった孔が微かにひくひくと動いていた。
指で入り口を押すと、「はぁっ」と声をあげてエオメルの身体が跳ね上がった。
「動かないでください」
ファラミアはかれの足をしっかりと抱えると、膝が胸につくくらい押し上げた。
テーブル上でエオメルの全てが完全に晒される。
扇情的な光景に、ゴンドーリアンのクールな白皙が赤く染まった。
「いい眺めだ−−こんな所まで丸見えですよエオメル殿」
熱く囁きながら、ファラミアの指がぐっとかれの後腔に差し入れられた。
「ファ、ファラミア殿・・・!」
今まで弟君の愛撫に身を任せてただ喘いでいたエオメルは、さすがに経験したことのない異物感に動揺した。
恥ずかしい格好をさせられ誰にも見せたことのない部分をあらわにされても、まんざら嫌な気はせずに快感を感じていたのだが、侵入してきた相手の指に大胆に内部を掻きこすられて、急に危機感を覚えたのである。
「やめてくださいッ、そんなところを」
身体を左右にねじってエオメルは抵抗した。
「暴れちゃ駄目ですよ、怪我をします」
「だ、だって−−もうよしてください、触らないで・・・!」
「でも指で馴らしておかないと、あなたが辛いでしょう」
そう言いつつ、ファラミアが指を2本に増やした。
「あァッ−−!」
くの字に曲げた指でぐりぐり犯され、エオメルがアッアッと声をあげる。
「ほら、指だけでもかなり良い気持ちでしょう?一緒にこちらも・・・」再びエオメルの固いペニスを握り締めると、指で強弱をつけながらファラミアは撫でさすった。
「前と後ろを一緒に弄られるのはどうですか」
性器への愛撫に連動させて肛門内を掻き回しながら、弟君はかれの耳元で熱く囁いた。
エオメルは相手の頭を掴んで金色の巻き毛をくしゃくしゃにかき乱しながら「あッあん、あぁ〜んッ!」などとマークの騎士軍団長とも思えぬ声をあげるのだった。
ねじり込んだ指で内壁を刺激していたファラミアは「だいぶほぐれて来ましたね」と言って、指を抜いた。
そしてペニスを掴んでいた手も離してしまった。
エオメルは大股開きにされた太腿をビクビクと痙攣させながら、「ま・・・待ってください、わたしはまだ・・・」と切なげな声をあげて弟君のほうに手を伸ばした。
「少々お待ちを。すぐにあなたの欲しいものを差し上げます」
ファラミアは口元に笑みを浮かべつつ、衣服の前をはぐった。
エオメルの押し上げられた足の間に身体を入れると、ファラミアは相手の尻の肉をつかんでかき分け、その中心部に自らのものをあてがった。
散々なぶられて秘所をジンジンと疼かせていたエオメルは、弟君の性器の先端にぐいと押されて「はぁ・・・っ」と快感の声を上げて仰け反った。
だが、すぐに今までとは全然違う太いものがめりめりと侵入してくる感触に驚いて身体を固くした。
「な、何ですそれは!?」
「何って・・・わたしのペニスですよ」
エオメルの悲鳴のような問いかけに、ファラミアは顔をしかめながら答えた。かれは、気を抜くと押し戻されてしまいそうなロヒアリムの狭い空間をこじ開けながら、ゆっくり突き進んでいくことに集中していた。
「そ、そんな・・・駄目です、やめてくださいファラミア殿・・・!」
「大丈夫です。そっとしますから」
ゴンドーリアンの熱く脈打つものによって、今まで経験したことのないほど肛門が押し広げられる異様な感覚に、エオメルは「あっ・・・ああっ・・・は、入ってくる・・・!」と髪を振り乱して声をあげた。
ようやく根元まで納めると、ファラミアは満足の吐息を洩らしてエオメルの髪を撫でた。
「よく締まって、熱い・・・。あなたは今までにこういう経験はおありなのかな?」
「あ、ありませんこんな事」
エオメルは太く固いものに秘部を占領された苦しさにはぁはぁと息を吐きながら答えた。
そして「お願いです、抜いてください」と懇願した。
ファラミアはかれの顔を近々と覗き込みながら「すぐには抜けませんよ。わたしが達してからじゃないと」と告げた。
「じゃ、はやくイって下さい、苦しい・・・!」
大きな瞳を涙で潤ませた軍団長に、執政家の公子は「ならあなたも協力してくださいね?」と笑いを含んだ声で言った。
「ただし、初めてでは少し辛いかもしれませんが・・・」
ファラミアがぐいっと腰を動かすと、「ひぁッ」とエオメルが悲鳴を上げた。
「痛いですか?」
「い、痛いです、すごく!」
「そうですか、でも仕方ありませんね」
と涼しい声で言って、さらに腰を突き上げる弟君であった。
グッグッと規則的に打ちつける動作に、エオメルが「そんなに激しく動かさないで下さいッ」と泣きそうな声を出す。
「このくらいで苦しいんですか?わたしはすごくイイ感じだが・・・」
「何故そんなに冷静なんです!?」
「あなたが昂奮しすぎているんですよ」
そうクールな口調で話すファラミアだったが、かれ自身も内奥にびりびりくるような快感を感じていた。エオメルの熱い体内はかれのものを咥えこんで、うねりながら締め付けている。
「こうすれば、少しは楽でしょう」
ファラミアは突き上げながら、またエオメルの性器を愛撫し始めた。
白い指が上下する。
「あッ・・・あぁ・・・ッ」
か細い声をあげてエオメルの咽喉がのけぞった。手の中のペニスが大きく揺れる。
「まだ駄目です」
気配を察したファラミアは、ロヒアリムの性器の根元をギュッと指で締めてかれの射精を阻止した。
「ひっ、ああ!」
放出できない疼痛に、エオメルは相手にしがみついて腰をのたうたせた。
「嫌だッ、いかせて・・・っ」
あえぎながら願うかれを、ゴンドーリアンは優しげな顔で見下ろしながら「わたしがもう少し楽しんでから」と答えたのだった。
私室のテーブルの上で執政家の次男の性器を受け入れさせられ、激しく揺すりあげられているエオメルは、絶えまなく乱れ声を上げ続けた。
「あっあんっ、ファラミアッ、ぁあっ」
ファラミアのほうも端正な顔を快楽に歪ませて、歯を食いしばりながら腰を打ちつけている。
意地悪な指によって射精を封じられたエオメルは、突き刺さるような性器の痛みと肛門を犯される快感にわれを失って「あぁーッ・・・だ、だめです、おかしくなりそうだぁ・・・ッ」と何度も喚いた。
やがてファラミアが「ああ・・・わたしのほうも、もう・・・!」とかすれた声で言った。
そして一際凄まじく突きあげる。
「ああああーーー!」
エオメルは絶叫した。
その時、ようやく解放されたペニスが熱い迸りを飛び散らせ、ファラミア自身も「うあ・・・ッ」と感に堪えぬ声をあげてロヒアリムの中に注ぎ込んだ。
ようやく体内から客人の性器が引き抜かれた。
だがエオメルは過呼吸寸前の状態で、足を広げたまま卓上ではぁはぁと息を吐いていた。
「大丈夫ですか」
すでに息を整えていたファラミアが、かれを抱き起こす。
そしてよいしょ、とお姫様抱っこして寝台に連れて行った。
腕や足元にまだまとわり付いていたエオメルの衣服を全部脱がせると、執政家の公子はロヒアリムの横たわった全裸姿を惚れ惚れと見下ろした。
「あなたの身体は見事ですね」
無駄のない筋肉に覆われた引締まった身体を感嘆のため息と共に撫でられる。
まだ朦朧としたままのエオメルは相手の指の動きに合わせて「ん・・・」と呟きともつかぬ声を出していた。
やがて枕元でファラミアが衣服を脱ぎ捨てているらしい衣ずれの音が聞こえてきた。
そしてエオメルの身体をまたぐようにして、ベッドに乗ってくる。
快感の残照にぼんやりしていたエオメルは、自分の上になったやはり全裸のファラミアの下腹部をなにげなく見やった。
するとそれが再び巨きくそそり勃っているのを目にして「ひぁッ」と変な声をあげた。
「ファ、ファラミア殿、それ」
相手は照れた笑みを浮かべて言った。
「あなたがあまり良すぎるから・・・夜は長いんです。もっと愉しみましょう」
「無理ですよッ!わたしはもう」
目を見開いて手足をばたつかせるエオメルの頬を手で挟むと、弟君はじっとかれを見つめた。
−−その底知れない青い瞳に捉えられると、どうも抵抗する気力を失ってしまうエオメルである。
「あなたほど魅力的な人は他にいない・・・」
そう囁きながらファラミアはエオメルに口づけた。
逃れようもなく・・・舌をからませあいながら、かれはゴンドーリアンの首に腕をまわしたのだった。
再び太腿を押し開かれて貫通されたとき、エオメルは相手に向かって呆然とした口調で言った。
「ファラミア殿、あなたは・・・わたしたちは・・・いったい何をしてるんでしょう」
「さあね」と首を傾げてファラミアがくすくす笑う。
そしてすぐにかれの中に深々と突き刺したものを大きく動かしはじめる。
「アッ、ま、また、そんな凄い・・・!」
のたうちながら喘ぎ叫ぶエオメルに、「でも、初めにわたしを誘惑したのはあなたの方ですから」とゴンドールの貴公子は少し意地の悪い声音で言うのだった。
翌朝はやく、一部の隙もなく身支度を整えたファラミアが厩舎に入っていくと、東谷のエオレドたちはみな気圧されたようになって頭を下げた。
「エオメル殿がくださると言っていた馬はどれかな」
そう言うと、一人の騎士が「こちらです」とかれを手招いた。
艶々と身体を輝かせた、黒毛の牡馬がかれの為に用意されていた。凝った装飾の鞍がついている。
「これは、実に見事な馬ですね」と言いながら馬首を撫でる。
「ローハンの駿馬は−−どんなにか手懐けるのが困難な暴れ馬なのかと思っていたが・・・以外に良く躾けられていて毛並も美しい・・・」
ファラミアはそう低く呟いて、口元に笑みを浮かべた。
そして馬を引き出しながら、エオレドたちに向かって言った。
「それでは、この馬を頂いていきます。部下たちが心配しているだろうから、わたしは今すぐ出立します。エオメル殿はまだお休みのようなので挨拶はしませんが、わたしが感謝していたと伝えていただきたい。そして、替わりに置いて行く牝馬が子を生んだらまたこちらに立ち寄ります」
かれは、そう言って馬にまたがった。
そしてかるく騎士たちに手を振ると、手綱を握ってアルドブルグ館の城門に向かって駆けて行った。
ロヒアリムたちは、金髪を朝日にきらめかせながら馬を操る貴公子の姿が、街道の向こうに消えるまで見送っていた。
20041212up
やり逃げかー!
|
|