 図解編
図解編 登記できる権利と第三者
トップページに戻る 目次ページに戻る
 図解編
図解編
登記できる権利と第三者
トップページに戻る 目次ページに戻る
物権にかかる第三者への対抗要件は、不動産が「登記」(177)、動産が「引渡し」(178)です。
債権の場合は「確定日付」のある通知、債務者の「承諾」、確定判決などの「債務名義」、特定の債権には「登録」、手形には「裏書」などがあり、登記できるものは賃借権や売買の買い戻し契約など限られています。
(図解の「権利義務の成立と第三者への対抗」もごらんください。対抗要件は夫婦の財産や相続財産にもかかわります。)
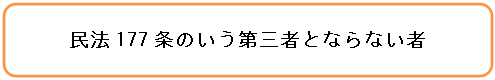 |
民法から離れて不動産登記法に寄り道しますと、同法第5条の見出しは「登記がないことを主張できない第三者」です。
どんな者と思えば、
①詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた者、
②他人のために登記を申請する義務を負う者です。
これらの者は、物権の変動を知っているので「悪意の第三者」に当たります。
良い悪いでなく、知っていたか否かに注意してください。
②は登記義務者から委任を受けた司法書士だけでなく、制限能力者の法定代理人、法人の理事などの代表権者、不在者の財産管理人が含まれます。
この5条の規定する者に類する者は「背信的悪意者」と呼ばれています。
未登記の取引の仲介者、未登記につけこんで嫌がらせや暴利を得る者も民法117条の第三者に当たらないとされています。
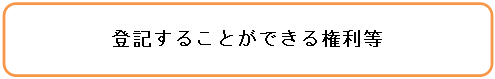 |
不動産登記法第3条は登記することができる権利等を定めています。
あげられているのは、①所有権 ②地上権 ③永小作権 ④地役権 ⑤先取特権 ⑥質権 ⑦抵当権 ⑧賃借権 ⑨採石権の9つだけです。
①から⑦までが物権で、債権は⑧だけです。
物権でも、占有権・入会権・留置権が含まれていません。
もっとも、登記には不動産登記のほかに商業登記もありますが、民法177条は「不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い」とありますのでこの条文だけではないことに注意しましょう。
物権の内容で区分すれば次のようになります。
土地: 所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権
建物: 所有権、先取特権、質権、抵当権
建物の方が土地より少ないのは、土地の利用権である地上権、永小作権、地役権が含まれないからです。