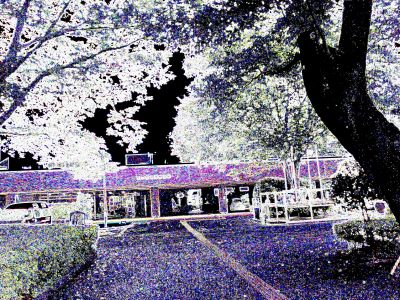
ラブレター
商社に勤めるOL3年生の香川京子はきびきびと閑静な住宅街を歩いている。この住宅街に京子の自宅がある。両親と3人暮らし。父親は資産家で京子の邸宅もかなりの大きな家で、3人で暮らすには幾分大き過ぎる造りである。帰宅した京子は台所で夕飯を作る母に挨拶をする。
「ただいま。まあ、いい臭い」
「おかえり、きょうはお前の好きなグラタンですよ」
「わあ、うれしい」
そう言うと、2階の自分の部屋に向かった。10帖の洋間。その一角にある机の上に向かう。手紙が置かれていた。
「あら、珍しい。紙の手紙?」
着替えもそこそこ珍しい手紙を手にした。今では連絡はすっかりEメールばかりである。差出人は小野寺祐一となっている。住所は書かれていない。字体は印刷のように綺麗に書かれている。ワープロの印字である。
「誰かしら?」
名前は書いてあっても、京子には全く心当たりのない名前である。封を切る。便せん2枚の手紙である。手紙を広げると整った活字が並んでいた。これもワープロである。
*
突然、このようなお手紙を差し上げるご無礼をお許しください。
貴方様の姿をここから何度となくお見掛けするうち、いつの間にか私の心と頭の中は貴方様のお姿で一杯でございます。今、私の心はとても苦しい。
寝ても覚めても貴方様のお姿ばかり。貴方様をただただお慕いするしかないふがいない私の性格をお察しいただきたいと存じます。今にも手が届く距離にいるのに、何も行動に移せない。この苦しみから逃れたいがため、このようなご無礼なお手紙を差し上げる覚悟をするに至りました。今書いている私は羞恥心に満ち満ちております。このような手紙を貴方様に差し上げてしまう。それもこの苦しい私の胸のうちを知っていただきたく筆をとった次第でございます。しかしながら、破っては捨て、破っては捨て、この手紙も何度、書いたものか数えきれません。恐らくこの手紙も貴方様のお目に触れることもなく、きっと捨て去られるのでありましょう。
でも、もう、この苦しさ、どうにもならない。貴方様に救っていただきたい。私と貴方樣だけの秘密の合図を考えました。もし、この私を救っていただけるのでございましたら、この同封したハンカチを頭上高く右左に振っていただけますでしょうか。
最後に、この手紙が貴方様に届くとき、それは私がもうとことん追いつめられているときでございます。
小野寺祐一
*
「なに、これって? ラブレター?」
京子はこの手紙を読み終えて嫌悪感で鳥肌が立った。封筒の中に手紙と一緒に20センチ四方の黄色い布切れが入っていた。これを振れということは分かった。しかし、実に変な合図である。私がいつ振るか、時間の指定もないし、何処でこれを振ればいいのか、場所の指定もない。ただ、振れというのはあまりにもこの男には思慮が足りない。
それと、自分の素性を全く明かさず会えと言うのはあまりにも身勝手ではなかろうか。いつも見かけているのであるなら、直接、渡すこともできるはずである。
一歩譲って、もし、この小野寺なる男に会って、彼の間に何の感情も生まれないとき、この男は次にどういう行動を起こすのであろう。そう思うと京子は恐怖で体が震えた。自分の周囲に異様な空気の冷たさを感じた。
改めて机の上に置いた封筒を見た。切手が貼っていない。まさか、直接家のポストに入れた。京子は部屋を飛び出すと、台所にいる母の元に走った。
「母さん、この封筒、ポストから取ったの、いつ?」
「何です? そんな封筒、今日は取っていないし、おまえの部屋にも持って行ってないですよ」
「そんな、あたしの机の上にあったのよ。これ」
「じゃ、お父さん? でも、お父さん、きょう、残業だって、さっき、電話があったわ」
返す言葉を失った京子は不可思議な封筒を持って部屋に戻った。誰がこの机の上に置いたのか。机に向かって座った。
そのとき、頭の上で音がした。京子は音のする天井に顔を向けた。天井に丸い3センチほどの円形の染みがある。立ち上がってその染みを見ようとした。よく見ると染みではなくどう見ても穴である。更に目を凝らす。暗い穴の奥に何かが動いている。更に目を凝らした。それはどう見ても目であった。次の瞬間、目が瞬きをしたのが分かった。
「早くハンカチ振ってくれないかなあ」
穴の奥から男の低い呟く声が聞こえてきた。
|