Polaxは連続撮影した画像から恒星の移動量を正確に表示し、それを元にユーザが極軸セッティングを行います。 まず望遠鏡を南中の星に向け極軸の方位角(東西方向)を修正していきます。 カメラを望遠鏡に取り付け、南中の星を露出10〜20秒程度で連続50〜100枚ほど撮影しFITS形式で保存します。 このとき画面を必要最小限にトリミング撮影・保存すると時間とHDD容量を節約できます。  Polaxを立ち上げ、メニューバーから「計測(K)」->「追尾計測(T)」をクリックし追尾計測画面を表示します。 「開く」をクリックして保存したファイルすべてを選択しリストアップします。 ファイルを選ぶときCtl+Aを押すとフォルダ内にあるすべてのファイルを選択できます。 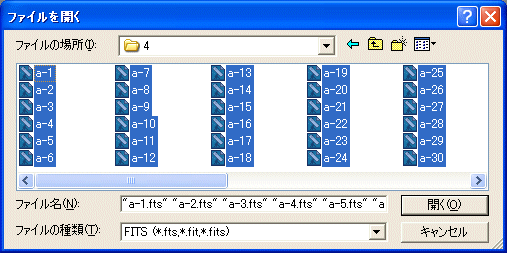 次に、「計測開始」をクリックするとリストアップされたファイルを自動的に読み込み、画像内の恒星の重心位置を解析します。 解析された重心位置はXY座標に表示されます。 座標をX方向に選択するとX軸方向の時間的移動量が表示され、同様にY方向を選択するとY軸の時間的移動量がグラフ表示されます。 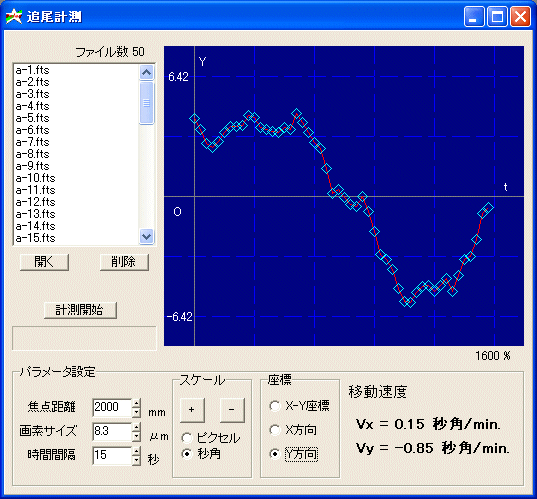 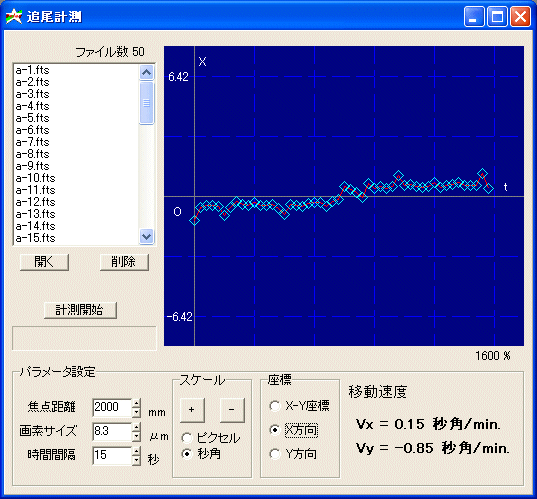 パラメータの焦点距離、画素サイズ、時間間隔をご自分のお使いの機器に合わせてください。 X方向を東西、Y方向を南北に合わせると、通常X方向には周期的グラフが現れ、Y方向には直線的グラフが現れます。 方位角修正にはY方向の直線の傾きが平らになるよう修正・撮影・計測を繰り返し行ってください。 方位角修正が終わりましたら、次は望遠鏡を北東または北西の方角、高度45度くらいの恒星に向け同様の作業を行います。 ここでもY方向の直線の傾きが平らになるよう高度修正を行ってください。 もし、北東または北西の方角の星を撮影できない場合には、南中の星を使い恒星の平均移動速度がゼロになるよう追い込めば、高度修正もできます。 この場合、撮影枚数を増やして波形グラフが何周期も現れるようにし、平均的な傾きがなくなるよう修正・撮影・計測を繰り返し行ってください。 目標値 南北方向の移動量を表す直線の傾きが毎分1ピクセル以下になればまずまずです。 0.1ピクセル以下になれば十分ですが、赤道儀によっては細かい角度修正を行うことができないものもありますので、目標値の限界は赤道儀に依存します。 こんなときPolaxを使ったファイン修正が必要です。 1、極軸望遠鏡を使ってセッティングした後の微調整 2、望遠鏡を載せ換えたとき 3、ガイドミスが多いとき 4、地盤がゆるいとき 5、設置型赤道儀でも長期間経過したとき 6、新築の建物や新しく地盤を固めてから数ヵ月後 TOP |