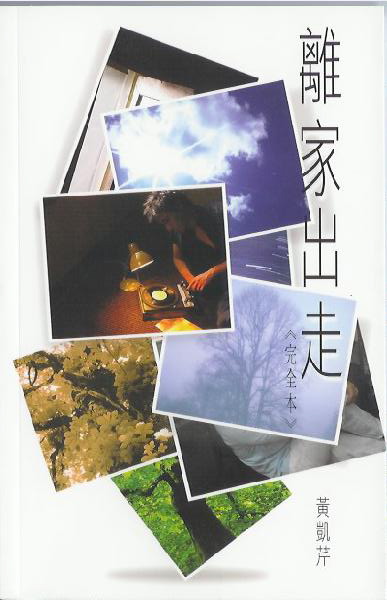



|
エッセイ集 「離家出走《完全本》」より〔重生〕
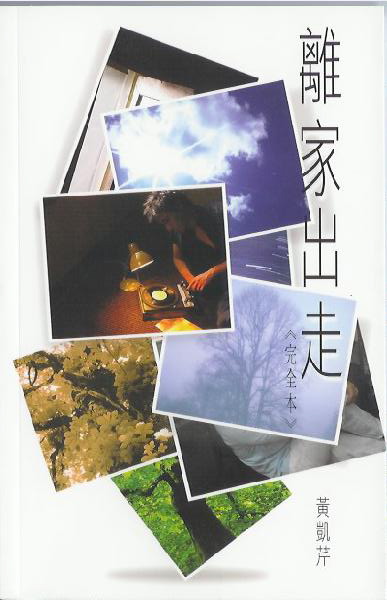 |
 |
 |
 |
| 2003年8月に発表されたエッセイ「離家出走《完全本》」より。 このエッセイ集の最初に収録されている〔重生〕はカナダに移民したクリスが香港での思い出の品々を処分するためにガレージセールをしたことが書かれてます。過去を立ち切るために処分する決心をしたんじゃないかと私は勝手に思ってます。 その後事あるごとに物を整理するのにガレージセールをしていたようです。クリスのものなら私も買いたいわ。 |
|
〔重生〕 |
| たくさんたくさんのものを背負い家を出た。 ついに、過去のものを処分する時が来た。 いくつかスーツケースに、たくさんの古い服が詰まっている。大部分が2〜3回しか着ていないので、厳密に言えば、みんな新しい服だ。例えばこんな形で捨ててしまうのは、もったいない。でも救世軍に送っても、断られるかもしれない。というのも誰の目にも明らかにステージ衣装だとわかるようなものがたくさんあるからだ。こんな服を路上生活者が着ているところは想像できない。 偶然町中で、よく人々が自分の家の前、道路や歩行者道の脇の草の上で、古着、古いものなどを売っているのを見かける。こうして僕はガレージセールとは何なのかを学んだんだ。 何でも売ることができる。 たくさんの人が、町中、新聞や雑誌などの小さな広告を見て、時間と場所を書き留め、朝早くからお宝探しにやってくる。古物商の店主やコレクターまでもが新しい宝探しに来ることさえある。 古いものを捨て、新しいものを迎える。 ...これは僕がある音楽賞の授賞式で着たものだ... 思い出の中に生きたくないので、わざと物思いに耽ることはしなかった。 ガレージセールの日が来た。一晩中眠らず、物を分類し、値段を付けるのに忙しくしていた。同時に、お別れを言うのにも忙しかった。かつて僕を守ってくれたコートにお別れをする、かつて僕を助けてくれたピンにお別れをする、すべてのかつてにお別れをして、ちょっと感傷的になった。でも、僕は過去の歴史と夢の中に自分を留めておくことができない。どんな時であれ、目が醒めれば、目の前の事実と向き合わなければいけないことを僕はわかっている。 朝から夜まで、とてもたくさんの見知らぬ人や近隣の人が来て、家の中も外もにぎやかだった。彼らは僕の物品はとても特別で高価だと褒めてくれた。10ドル80セントでイタリアブランドのコートが買えるなんて、他にどこにある?これは実に彼らのラッキーデーだ。ある人は僕の古い革靴でさえ喜んで買って行ってくれた。これは確かに僕のラッキーデーだ。以前テレビのゲーム番組でもらった賞品で、表面にヨーロッパ18世紀の航海図が描かれている皮のケースは、芸術家の夫婦に気に入られた。彼らは選んだあと、上にガラス板を載せたらティー・テーブルになると言っていた。実際、すごく手放し難いんだけど、自分が使わないものを、どうして欲しい人にあげないでいるのか?すでに手にしながら、そのへんに放っておくのは、人でも物でもとても不公平なことだ。 一人の外国籍の不動産業の友人と彼の奥さんが一気に20数件の服、皮製品それにコートを買ってくれた。彼自身は僕よりもずっと背が高くて、服を着ると、明らかにサイズが合っていないにもかかわらず、それでも彼は無理矢理いいと言っている。約三週間後、僕は彼がそれぞれ僕のコートと僕のシャツを着た姿を撮影した大小の2枚の広告が、バス停の広告に出ているのを見た。横たわった姿のあの写真は、しかも目につきやすい長椅子の背もたれに貼ってあった。 僕はまだ覚えている。僕はあの広告にしばらく釘付けになり、かつて自分の服であったものに、他の人の顔と身体にすげ変わっているのを見て、すごく不思議な気分だった。 僕はといえば、あの日の夕方、残ったものや売り出さなかったものを片付けている時、何かを洗い流したようにすっきりした気分だった。 |